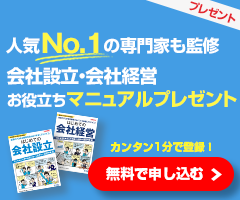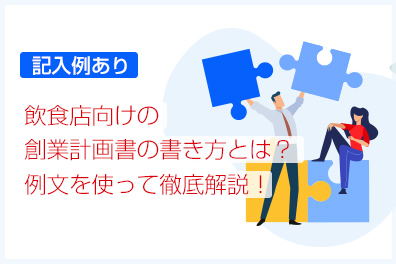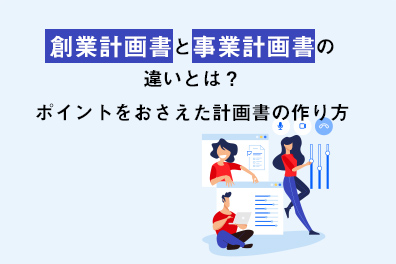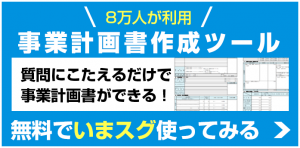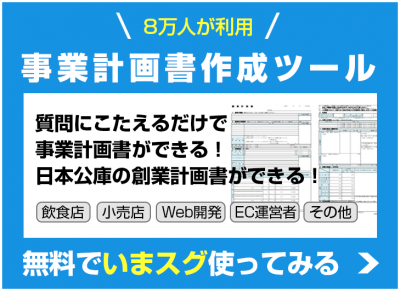融資を成功に導く、借入申込書の正しい書き方を起業のプロが徹底解説
起業や新規事業の立ち上げ、事業拡大には資金調達が不可欠です。金融機関からの融資は、その有力な選択肢のひとつですが、融資を受けるためには、まず借入申込書を正しく記入し提出する必要があります。しかし、はじめて融資を申込む方にとっては、借入申込書の書き方や注意点が分からず、戸惑うことも多いでしょう。
そこで本記事では、融資を成功に導くための借入申込書の正しい書き方について、起業のプロが徹底解説します。本記事を読めば、借入申込書の各項目の意味や書き方、注意点が理解でき、自信を持って融資の申込みに臨めるようになります。不備なく借入申込書を作成し、スムーズな資金調達を実現するための第一歩を踏み出しましょう。
8万人が利用した事業計画書作成ツール
ブラウザ上の操作で事業計画を作成、創業計画書もエクセルでダウンロード可能
元日本政策金融公庫の融資課長として5000名以上の起業家を支援した上野アドバイザー。現在は、資金調達の専門家として活躍されております。融資を検討されている方はぜひご相談ください。
著書「事業計画書は1枚にまとめなさい」「起業は1冊のノートから始めなさい」など。
プロフィールを見る>>

1.借入申込書とは
借入申込書は、企業や個人事業主が金融機関から事業資金の融資を受ける際に、必ず提出を求められる書類です。この書類には、融資希望額・資金の使い道・返済方法など、融資の申込みに関する詳細な情報を記載します。
金融機関は、提出された借入申込書の内容を基に審査を行い、融資の可否や融資条件(金利や返済期間など)を決定します。つまり、借入申込書は、融資を受けるための第一関門であり、その記載内容が融資の成否を大きく左右するといえるでしょう。
本記事では、数ある金融機関のなかでも、とくに日本政策金融公庫(略称:日本公庫)の借入申込書に焦点を当てて解説します。日本公庫は、政府が出資する政策金融機関であり、新規開業や中小企業・小規模事業者を資金面で支援することを主な目的としています。
そのため、民間の金融機関と比較して、創業間もない企業や小規模事業者でも融資を受けやすいという特徴があります。これから起業を目指す方、事業をはじめて間もない方にとって、日本公庫は非常に心強い味方となるでしょう。
参考:日本政策金融公庫「各種書式ダウンロード(借入申込書)」
2.借入申込書の書き方
日本公庫の借入申込書は、一見すると記入項目が多く複雑に感じるかもしれません。しかし、一つひとつの項目を丁寧に確認していけば、決して難しいものではありません。
ここでは、日本公庫の借入申込書の各項目について、具体的な書き方や注意点をくわしく解説します。正確な情報を記入し、金融機関からの信頼を得ることが、融資成功への近道となりますので、しっかりと把握しましょう。
参考:日本政策金融公庫「各種書式ダウンロード(借入申込書
記入例)」
1)お申込名
法人であれば、会社名を正式名称で記入します。「株式会社〇〇」のように、(株)などと省略せずに記入しましょう。個人の場合は、氏名を記入します。
2)お申込金額
希望する融資金額を記入します。通常の融資では、月商の3〜6カ月分が目安とされています。
ただし、日本政策金融公庫総合研究所の「2024年度新規開業実態調査」によれば、開業時における資金調達額は平均1,197万円であり、そのうち金融機関からの借入額平均は780万円となっています。自己資金との比率などを考慮しながら、必要な金額を記入しましょう。
3)お借入希望日
融資を希望する日を記入します。はじめて日本公庫と取り引きをする場合、審査や手続きに時間がかかるため、早くても入金までに3週間~1か月はかかります。そのため、3週間以降の日付を記入するのが無難です。
あまりに近い日付を記入すると、「資金繰りに相当困っているのではないか?」と金融機関に警戒される可能性があるので注意が必要です。
追加融資の場合は、審査がスムーズに進めば、1週間から2週間程度で融資が実行されることもあります。その場合は、1週間後や2週間後の日付を記入しても問題ありません。
4)ご希望の返済期間
返済期間は、長ければ長いほど毎月の返済額は少なくなります。基本的には、できるだけ長い期間を設定する方が、返済は楽だといえます。
しかし、長くすると「利率が高くなる」「元金が減るのが遅いため、次の融資が必要なときに支障をきたす可能性がある」という問題があります。
日本公庫の融資制度では、「運転資金10年以内、設備資金20年以内」とされていますが、じっさいには、運転資金なら5〜7年、設備資金なら5〜10年に設定されることが多いです。
運転資金と設備資金の割合にもよりますが、借入金額が小さい場合は、5年の設定となることもあります。
自社の返済力を冷静に分析して、適正な返済期間になるように融資担当者と協議しましょう。
ちなみに、日本公庫は融資後の返済条件の変更(「条件変更」または「リスケ」といいます)にも柔軟に対応してくれます。万一、経営状況が悪化し、返済が困難になった場合は、早めに相談するようにしましょう。
ただし、条件変更を行うと、信用力が低下してしまうことに留意が必要です。
5)元金据置
元金据置とは、融資を受けてから一定期間、元金の返済を猶予してもらい、利息のみを支払うことです。据置期間中は、毎月の返済負担を軽減できるため、事業が軌道に乗るまでの資金繰りに余裕が生まれます。
日本公庫の場合、元金の据置期間は最長5年以内です。ただし、融資金額が小さい場合は、据置期間を設定できないこともあります。
参考:ドリームゲート「返済期間や方法で総返済額はどう変わる?
【日本政策金融公庫の創業融資】」
6)毎月のご返済希望日
毎月の返済日を記入します。取引先からの入金や、各種の支払いを考慮し、資金繰り的にもっとも余裕がある日を希望しましょう。
7)ご返済金のお支払方法
返済金の支払い方法を選択しますが、預金口座からの自動引き落としが一般的です。インターネット専業銀行からの口座振替による返済も可能となっています。日本公庫への申込み時点で、会社名義の預金口座をまだ開設していない場合は、この項目を記入する必要はありません。
8)資金のお使いみち
融資を受けた資金の使い道を、設備資金と運転資金にわけて、具体的な内容を記入します。設備資金は、工場や店舗の建設・改装、機械設備の購入など、使い道によっては低利率になることがあります。そのため、設備資金がある場合は、優先的に記入しましょう。
運転資金の内容が、人件費や広告宣伝費の場合は注意が必要です。これらの支出は本当に売上に繋がるのか不透明であるため、金融機関が納得できるように説明が必要です。
なお、融資を受けた資金を、申告した用途以外に使用することは、重大な契約違反となります。
とくに設備資金で融資を受けた場合は留意が必要です。たとえば「車を買う」としていたのに、その資金を運転資金に使用するなどです。資金使途違反は行わないよう、十分にご注意ください。
万一、当初予定していた内容とは別の資金使途に使用する場合は、事前に金融機関へ相談しましょう。
9)創業年月
法人の場合は、登記簿謄本に記載されている「会社設立年月日」を記入します。個人の場合は、税務署に提出した開業届に記載されている「開業日」を記入しましょう。
10)業種
営んでいる事業の業種を記入します。「日本標準産業分類」を参考に、該当する業種を記入しましょう。日本標準産業分類は、総務省のホームページなどで確認できます。
11)従業員数
現在の従業員数を記入します。役員やパート・アルバイトも含めた人数と、その内訳も明記しましょう。
12)お申込人または法人代表者の方のご家族
同一生計の家族がいる場合は、その家族の情報を記入する必要があります。
13)担保・保証の条件
担保や保証人の有無を選択します。日本公庫は、無担保・無保証の融資に積極的です。とくに創業融資の場合は、無担保・無保証で融資を受けられる可能性が高いので、積極的に活用しましょう。
ただし、2,000万円を超えるような高額融資を希望する場合は、不動産担保などの提供を打診されることもあります。
- 累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる
- 12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定
3.借入申込書を書くうえでのポイント・注意点
借入申込書の各項目の具体的な書き方について理解を深めたところで、さらに融資審査を有利に進めるためのポイントと注意点を確認していきましょう。
これらのポイントは、単に書類上の体裁を整えるだけでなく、金融機関に対して「返済能力がある」「信頼できる」という印象を与えるために非常に重要です。とくに、創業融資の場合は、実績がない分、これらのポイントをしっかりとおさえることが、融資成功の鍵を握るといっても過言ではありません。
1)インターネット申込みの場合は不要
日本政策金融公庫では、窓口での申込みだけでなく、インターネット経由での融資申込みも受け付けています。インターネット申込みの場合、借入申込書に記載する内容と同様の情報を、専用のウェブサイト上で入力していく形式になります。
そのため、あらためて紙の借入申込書を作成し、提出する必要はありません。入力内容に誤りがないか、しっかりと確認しながら進めましょう。
2)訂正印で訂正可能
紙の借入申込書に手書きで記入する場合、誤った情報を記入してしまうこともあるかもしれません。そのような場合は、修正液や修正テープを使用するのではなく、必ず二重線で誤った箇所を消し、その上に訂正印を押して修正しましょう。
3)社名はゴム印でOKだが、代表名は不可
会社名(法人名)の記入にはゴム印を使用しても問題ありません。しかし、代表者名は必ず自署で記入する必要があります。自署することで、代表者本人が融資の申込み意思を持っていることを明確に示すことができます。
4)創業時の借入金額の目安は自己資金の3倍
創業融資の場合、希望する借入金額の目安は、一般的に自己資金の3倍程度といわれています。たとえば、1,000万円の融資を希望する場合、最低でも300万円程度の自己資金を用意しておくことが望ましいです。
自己資金が少ないと、「借入依存度が高すぎる計画」「計画性がない」と判断され、融資審査で不利になる可能性があります。
5)据置期間は6ヵ月から1年程度にする
元金の据置期間は、長ければ長いほどよいというわけではありません。据置期間をあまりに長く設定すると、「事業を軌道に乗せるのに、そんなに時間がかかるのか?」「返済能力に問題があるのではないか?」と金融機関に疑念を抱かせる可能性があります。そのため、据置期間は、6ヵ月から長くても1年程度に設定するのが無難です。
6)法人は融資が決定してから銀行口座を開設する方法も
法人を設立したばかりの場合、銀行口座の開設に苦労することがあります。とくに、近年はマネーロンダリング対策などの観点から、金融機関の審査が厳格化しているため、法人口座の開設は容易ではありません。
しかし、日本公庫の融資が決定すれば、その事実が一定の信用となり、銀行口座を開設しやすくなる場合があります。融資決定の通知書などを持参し、金融機関に相談してみましょう。
また、中小企業の場合は、信用金庫に口座を開設することをおすすめします。信用金庫は、地域密着型の金融機関であり、地域の中小企業を支援することを目的のひとつとしています。
そのため、預金口座を開設するだけでも歓迎されることが多く、将来的に信用金庫から融資を受けやすくなる可能性もあります。メインバンクとして利用することで、長期的な信頼関係を築くことができるでしょう。
7)裏面は特に記入する必要なし
日本政策金融公庫の借入申込書の裏面には、「公庫におけるお客さまの情報の取扱に関する同意事項」や「連帯保証に関するご案内」「添付書類のご案内」が記載されていますので、確認しておきましょう。
「融資制度等のご案内のためのダイレクトメールの発送等」についての意思確認のチェック欄がありますので、不要な場合には「レ印」をつけておきましょう。そのほかには、とくに、記入する項目は設けられていません。
4.創業融資に不可欠な事業計画書の作成は「ドリームゲート」
創業融資を受けるためには、借入申込書だけでなく、事業計画書の提出も必要です。事業計画書は、事業の将来性や収益性、返済能力などを金融機関に説明するための重要な書類です。しかし、はじめて事業計画書を作成する方にとっては「何を書けばよいのか」「どのように書けばよいのか」がわからず、頭を悩ませることもあるでしょう。
そこでおすすめなのが、起業・経営支援サービス「ドリームゲート」が提供する事業計画書作成サポートツールです。ドリームゲートのツールは、質問に答えていくだけで、かんたんに事業計画書を作成できます。このサポートツールを活用することで、融資担当者に響く事業計画書を作成し、創業融資の成功率を高めることができます。
融資の審査では、事業計画書の内容が非常に重視されます。ドリームゲートのツールは、金融機関が評価するポイントを熟知しているため、あなたの事業の強みを最大限にアピールし、融資の実現を力強くサポートします。
- 累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる
- 12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定

元日本政策金融公庫の融資課長として5000名以上の起業家を支援した上野アドバイザー。現在は、資金調達の専門家として活躍されております。融資を検討されている方はぜひご相談ください。
著書「事業計画書は1枚にまとめなさい」「起業は1冊のノートから始めなさい」など。
プロフィールを見る>>