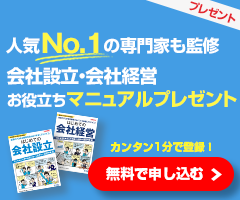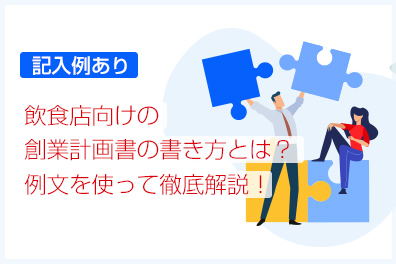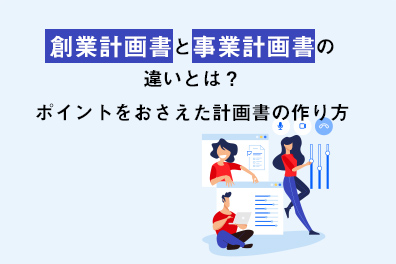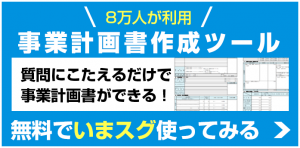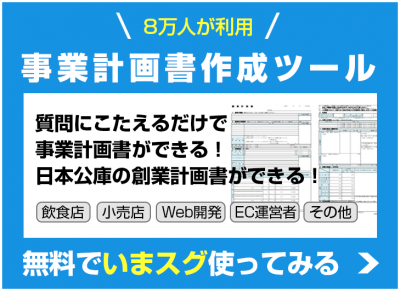「そんな方法があったのか」開業資金の集め方を融資のプロが徹底解説
「いよいよ起業!」と決意したものの、開業資金をどうやって集めればいいのか悩んでいませんか?
自己資金だけで足りるのか、融資を受けるべきか、あるいはほかに方法があるのか…。
夢を実現するためには、資金調達は避けて通れない課題です。しかし、資金調達の方法は多岐に渡り、それぞれにメリット・デメリットが存在します。また、手続きの複雑さなど、ほかにも理解しておくべきことがたくさんあります。
当記事では、融資のプロの視点から、開業資金の集め方を徹底的に解説します。自己資金の貯め方からさまざまな融資制度、そして近年注目の資金調達方法まで、具体的な例を交えながらわかりやすく解説します。
当記事を通じて、あなたにとって最適な資金調達方法を見つけ、不安を解消し、開業に向けて自信を持って一歩踏み出しましょう。
8万人が利用した事業計画書作成ツール
ブラウザ上の操作で事業計画を作成、創業計画書もエクセルでダウンロード可能
元日本政策金融公庫の融資課長として5000名以上の起業家を支援した上野アドバイザー。現在は、資金調達の専門家として活躍されております。融資を検討されている方はぜひご相談ください。
著書「事業計画書は1枚にまとめなさい」「起業は1冊のノートから始めなさい」など。
プロフィールを見る>>

- 累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる
- 12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定
目次
1.開業資金とは
開業資金とは、事業をはじめるために必要な資金のことです。どのような費用がかかるのか、金額の目安はいくらかなど、具体的に説明します。
1)設備資金と運転資金に大別される
開業資金は、大きく「設備資金」と「運転資金」の2つに分けられます。
設備資金とは、事業をはじめるために必要な設備や備品などを購入するための資金です。たとえば、店舗を構えるなら内装工事費や什器・備品の購入費、製造業なら機械や工具の購入費などが該当します。また、飲食店なら厨房設備、美容室なら美容機器など、業種によって必要な設備は大きく異なります。
運転資金とは、事業を運営していくために必要な資金です。具体的には、人件費・家賃・光熱費・広告宣伝費・仕入代金などが挙げられます。開業当初は売上が安定しない場合が多いため、少なくとも数ヶ月分の運転資金を確保しておくことが重要です。
参考:創業融資の運転資金は何か月分が妥当か?【元日本公庫融資課長が監修】
2)法人設立費用もかかる
個人事業主として開業する場合は法人設立費用はかかりません。しかし、株式会社や合同会社などの法人を設立する場合は、登録免許税や定款認証費用などの設立費用が発生します。近年では、設立費用が株式会社よりも安く抑えられる、合同会社を選択する方が増えています。
3)必要額は500~1,000万円が目安
開業資金として必要な金額は、業種や事業規模によって大きく異なります。日本政策金融公庫総合研究所の『2023年新規開業実態調査』によると、開業資金の平均は1,027万円で中央値は550万円であり、長期的にみると少額化の傾向にありますが、500~1,000万円の範囲で必要となるケースが多いようです。
参考:日本政策金融公庫総合研究所『2023年新規開業実態調査』
4)法人成りが必要かしっかり検討する
開業当初は、個人事業主として事業をスタートし、軌道に乗ってきたら法人成りする、という選択肢もあります。法人成りには、税制面や社会的な信用度などのメリットがある一方、設立費用や会計処理などのコストも発生します。事業の規模や将来的な展望を考慮し、法人成りの必要性を慎重に検討しましょう。
- 累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる
- 12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定
2.開業資金の集め方①自己資金
開業資金を調達する最初のステップとして、まず検討すべきなのが自己資金です。自己資金とは、これまでコツコツと積み上げてきた貯蓄や、保有する資産を売却して得た資金になります。
融資を受ける場合でも、この自己資金比率が非常に重要になります。一般的に、金融機関は自己資金比率が高いほど、事業に対する熱意や計画性があると判断し、融資を実行しやすくなる傾向があります。目安としては、開業資金全体の30%以上を自己資金で賄えるように準備しておきましょう。
1)貯蓄
もっとも基本的な自己資金の調達方法は、毎月の収入から一定額を積み立てることです。給与天引きで自動的に貯蓄できる制度を利用したり、銀行口座を分けて管理したりするなど、工夫しだいで着実に資金を貯めることができます。
また、ボーナスや臨時収入を積極的に開業資金に充当することも有効です。目標額を設定し、計画的に貯蓄を進めていきましょう。
2)資産の売却
「貯蓄があまりない…」という場合でも、諦める必要はありません。保有している資産を売却することで、まとまった資金を調達できる可能性があります。
たとえば、使用していない不動産や自動車・価値が上がっている株式・不要になった骨董品など、売却できるものは意外と多いものです。ただし、売却には時間や手間がかかる場合があり、必ずしも希望どおりの価格で売却できるとは限りません。余裕を持って準備を進めることが大切です。
3)贈与を受ける
親族から贈与を受けるという方法もあります。資金調達の手段としては有効ですが、贈与税が発生する可能性がある点には、注意が必要です。
贈与税は、贈与額に応じて課税される税金であり、年間110万円の基礎控除を超える部分に対して課税されます。贈与を受ける際は、税理士に相談するなどして、適切な手続きを踏むようにしましょう。
4)再就職手当を利用する
会社を退職して、新たに事業をはじめる場合は、再就職手当の活用を検討してみましょう。再就職手当とは、失業保険の支給日数を残した状態で就職や開業をした場合に、規定の給付金を一括で受け取れる制度です。
この制度を利用することで、開業資金の一部を賄うことができます。ただし、受給資格や支給要件など、一定の条件を満たす必要があります。ハローワークに相談し、利用できるかどうか確認してみましょう。
自己資金を調達する方法は、決してこれらの方法だけに限りません。副業で収入を得たり、不用品をフリマアプリで販売したりするなど、工夫しだいでさまざまな方法があります。ご自身の状況に合わせて、最適な方法を検討してみてください。
3.開業資金の集め方②融資(デットファイナンス)
自己資金である程度開業資金を準備できたら、次に検討したいのが融資です。融資とは、金融機関からお金を借り、利息を付けて返済していく資金調達方法です。
自己資金だけで開業資金を賄える場合でも、低リスクで融資を受けられるのであれば、積極的に活用することをおすすめします。とくに日本政策金融公庫は、無担保・無保証で借りられる場合があるので、必ず確認しましょう。
1)政府系金融機関
政府系金融機関の中でも、とくに日本政策金融公庫の創業融資制度は、新規開業者の強い味方です。日本政策金融公庫は、国が設立した金融機関であり、創業支援に力を入れています。無担保・無保証で融資を受けられる場合もあり、創業時がもっとも融資を受けやすいので、積極的に利用することをおすすめします。
参考:日本政策金融公庫での創業融資の申し込みの全てを融資の専門家が徹底解説
参考:日本政策金融公庫の創業融資が大進化【元公庫融資課長が解説】
2)信用保証協会保証付融資
信用保証協会の保証付融資とは、信用保証協会が金融機関に保証することで、事業者が融資を受けやすくする制度です。金融機関が独自におこなうプロパー融資と比較して、保証料がかかる点が異なります。
しかし、開業時は信用力が低いため、プロパー融資を受けることは難しいのが現状です。信用保証協会の保証付融資を利用することで、融資を受けやすくなるだけでなく、返済実績を積み重ねることで、将来的なプロパー融資にも繋がりやすくなります。
ただし、代表者が保証人になることを求められるケースが多く、場合によっては貯金額など個人資産の記録の提出を求められることもあります。
参考:創業融資における信用保証協会の役割とは?|資金調達のプロが公庫と徹底比較
3)信用金庫・信用組合
信用金庫・信用組合は、地域密着型の金融機関であり、小規模事業者や地域住民に対して融資をおこなっています。規模が小さいため、個別対応に柔軟性がある点が魅力です。ただし、地域に根ざした事業を開業する必要があり、融資額が小規模で、金利もやや高めになる傾向があります。
参考:元・信用金庫の営業マンが明かす、信用金庫の融資審査の裏側とは?
4)制度融資
制度融資とは、自治体や商工会議所などが窓口となり、金融機関と連携して融資を提供するしくみです。信用保証協会が融資の保証をおこなうことで、事業者の負担を軽減しています。
ただし、利用条件が自治体や業種ごとに異なり、手続きが煩雑な場合もあります。また、地域に根ざした事業であることが求められるケースが多い点にも、注意が必要です。
参考:都道府県の制度融資
参考:市区町村の制度融資
5)ノンバンクのビジネスローン
ノンバンクとは、銀行以外の金融機関のことで、信販会社や消費者金融などが該当します。ノンバンクのビジネスローンは、審査が比較的緩やかで、スピーディーに融資を受けられる点がメリットです。しかし、金利が高い傾向にあるため、返済計画をしっかりと立てる必要があります。
6)手形割引
手形割引とは、取引先から受け取った手形を、満期日前に金融機関に買い取ってもらうことで、資金を調達する方法です。開業資金には向いていませんが、事業が軌道に乗った後には、資金繰りの手段として有効な場合があります。
4.開業資金の集め方③出資(エクイティファイナンス)
出資とは、企業の株式を投資家に引き受けてもらうことで、資金を調達する方法です。融資とは異なり、返済義務がないため、リスクが低く感じるかもしれません。
しかし、株主が増えることで、経営の自由度が制限されたり、株式の希薄化が起こったりする可能性があります。また、株式の上場や売却など、「エグジット」を見据えた計画が必要となる場合もあります。
投資家のタイプ(ハンズオン・ハンズオフ)や、相性があるため、よく見極める必要があります。
1)ベンチャーキャピタル(VC)
ベンチャーキャピタルとは、成長が期待できる未上場のベンチャー企業やスタートアップ企業に出資する投資会社や投資ファンドです。
ただし、事業計画や成長戦略を明確に示す必要があり、出資条件がきびしいケースが多くなります。
参考:【専門家監修】ベンチャーキャピタルとは?初心者でもわかりやすく解説
2)エンジェル投資家
エンジェル投資家は、個人でスタートアップ企業に出資をおこなう投資家のことです。ベンチャーキャピタルよりも少額からの出資が可能で、資金提供だけでなく、事業経験や人脈を活かしたサポートも期待できます。ただし、エンジェル投資家との相性も重要となるため、慎重に見極める必要があります。
3)社員持株会
社員持株会は、自社の株式を社員が購入・保有できる制度です。福利厚生として社員のモチベーション向上が図れるだけでなく、敵対的買収の予防によって、企業の安定的な成長を促す効果も期待できます。ただし、株式の管理や運営に手間がかかる点に注意が必要です。
4)他企業からの出資
事業提携などを目的として、ほかの企業から出資を受けるケースもあります。シナジー効果による事業拡大や、経営基盤の強化などが期待できますが、出資元の企業との関係性や、経営方針との整合性などを考慮する必要があります。
5.開業資金の集め方④そのほか
上記以外にも、開業資金を調達する方法はいろいろと存在します。
1)補助金/助成金
国や地方自治体が、特定の条件を満たす事業者に対して支給する資金です。返済義務がないため、資金調達の負担を軽減できます。ただし、申請手続きが複雑で、審査基準もきびしいため、事前の情報収集が重要です。
2)ビジネスコンテスト
ビジネスプランを競うコンテストで入賞することで、賞金や投資を獲得できる場合があります。資金調達だけでなく、事業の宣伝にも繋がる点が魅力です。ただし、注目されなければ資金調達は難しいため、ある程度
SNS などで影響力がある方や会社におすすめです。
3)クラウドファンディング
インターネットを通じて、不特定多数の人々から資金を調達する方法です。資金調達だけでなく、顧客獲得や商品・サービスの認知度向上にも繋がる可能性があります。ただし、目標金額に達しなければ資金調達できない点に注意が必要です。
4)ファクタリング
ファクタリングとは、売掛債権をファクタリング会社に売却することで、資金を調達する方法です。開業資金には向いていませんが、事業が軌道に乗った後には、資金繰りの手段として有効な場合があります。
5)資産の現金化(アセットファイナンス)
アセットファイナンスとは、保有する資産を担保に資金を調達する方法です。開業資金には向いていませんが、不動産や設備などを保有している場合は、資金調達の選択肢のひとつとなります。
6.事業計画書の作成なら「ドリームゲート」
開業資金の集め方は、自己資金、融資、出資、そのほかと多岐に渡り、それぞれにメリット・デメリットがあります。どの方法が最適かは、業種、事業規模、経営者の状況によって異なります。
資金調達を成功させるためには、まず、しっかりとした事業計画を立てることが重要です。事業計画書は、あなたの事業の将来像を具体的に示すものであり、金融機関や投資家からの信頼を得るために不可欠なものです。
「ドリームゲート」の事業計画書作成ツールを使えば、12業種に対応した事業計画書をブラウザ操作だけで作成できます。かんたんな質問に答えるだけで作成できるので、はじめての方にもおすすめです。
作成した事業計画書は、Excelファイルなどでダウンロードできるので、修正もかんたんです。無料で使えるので、まずは試してみてはいかがでしょうか。
当記事が、あなたの開業準備をスムーズに進めるための一助となれば幸いです。
- 累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる
- 12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定

元日本政策金融公庫の融資課長として5000名以上の起業家を支援した上野アドバイザー。現在は、資金調達の専門家として活躍されております。融資を検討されている方はぜひご相談ください。
著書「事業計画書は1枚にまとめなさい」「起業は1冊のノートから始めなさい」など。
プロフィールを見る>>