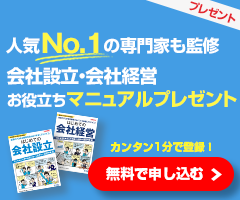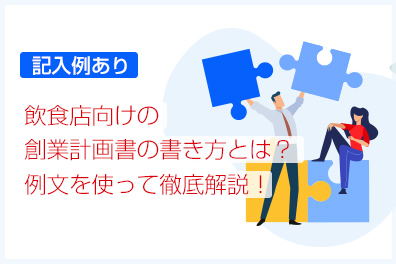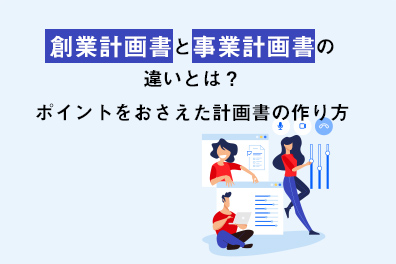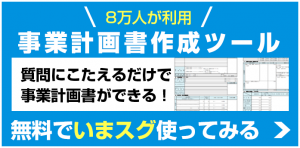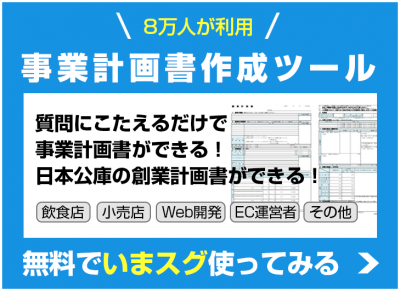開業資金の融資が受けやすい3つの金融機関を融資のプロが解説
はじめての起業においては、金融機関からの融資の可否が、事業計画の実現可能性を大きく左右します。融資を円滑に進めるためには、「どの金融機関を選ぶか」が極めて重要であり、その選択を誤ると貴重な時間と労力を浪費してしまう結果にもつながりかねません。
本記事では、融資のプロの視点から、開業資金の基礎知識や、融資を受けやすい金融機関などを具体的に解説します。さらには審査にパスするための実践的なポイントまでわかりやすくご紹介し、皆様の事業スタートを力強く後押しいたします。ぜひ、参考にしていただければ幸いです。
8万人が利用した事業計画書作成ツール
ブラウザ上の操作で事業計画を作成、創業計画書もエクセルでダウンロード可能
元日本政策金融公庫の融資課長として5000名以上の起業家を支援した上野アドバイザー。現在は、資金調達の専門家として活躍されております。融資を検討されている方はぜひご相談ください。
著書「事業計画書は1枚にまとめなさい」「起業は1冊のノートから始めなさい」など。
プロフィールを見る>>

目次
1.そもそも開業資金とは
開業資金とは、事業を立ち上げ、軌道に乗せるまでに必要となる費用を指し、主に「運営資金」「設備資金」「法人設立費用」の3つに分類することができ、それぞれの資金使途を明確にしておくことが、融資審査を通過するための重要な前提となります。
1)運営資金
運営資金とは、「運転資金」ともいいますが、事業を営むうえで必要となる資金のことです。具体的には、人件費、事務所の家賃や光熱費、広告宣伝費、仕入れ費用、交通費などが該当し、これらを最低でも6カ月分程度は見込んでおくことが、事業継続の安定性を金融機関に示すうえで肝要になります。
参考:創業融資の運転資金は何か月分が妥当か?【元日本公庫融資課長が監修】
2)設備資金
設備資金は、事業をおこなうために必要な有形の資産や設備を購入するための資金です。例として、店舗の内装工事費、厨房機器、製造機械、パソコン、車両運搬具などが挙げられます。これらの設備は事業の根幹をなすため、見積りを取得し、その金額の妥当性を明確に説明できるように準備しておく必要があります。
3)法人設立費用
個人事業主ではなく、法人として起業する場合にかかる費用です。具体的には、会社設立時の登録免許税、定款作成費用、専門家への報酬などが含まれます。これらの費用は事業開始前の初期段階で発生するため、自己資金で賄うのが基本ですが、融資の対象となることもあります。
- 累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる
- 12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定
2.開業資金の融資が受けやすい金融機関3つ
開業資金の融資を検討する際、起業家にとって有利な選択肢となる金融機関は限られています。通常の銀行では実績のない新規事業への融資は極めてハードルが高いため、まずは以下の3つの選択肢から検討をはじめるべきです。
これらの金融機関は、創業支援に特化した制度や役割を持っており、実績の浅いスタートアップでも融資の可能性が高まります。
1)日本政策金融公庫
創業融資を検討するならば、まず日本政策金融公庫(日本公庫)への相談が最優先事項です。日本公庫は政府系の金融機関であり、民間の金融機関ではリスクが高いと見なされがちな創業期の企業への資金供給を主な目的としています。
実績がなく、担保や保証人も用意できない起業家を支援するための制度が充実しており、民間の金融機関と比較して圧倒的に融資が受けやすい点が特徴です。また、日本公庫は金利も低めに設定されており、起業家にとって非常に利用しやすい条件が整えられています。
2)信用保証協会付き融資
開業資金の融資において、日本公庫以外の選択肢として可能性が高いのは、信用保証協会付き融資が挙げられます。信用保証協会とは、中小企業が民間金融機関から融資を受ける際に保証をする公的な機関です。信用保証協会付き融資は、地域の中小企業や小規模事業者の資金調達を支援するため、信用保証協会が融資の保証をおこなうことで、金融機関が安心して融資を実行できるようにする制度です。
起業家は、まず銀行や信用金庫などの金融機関に融資を相談してから、信用保証協会へ保証を申し込むという流れになります。金融機関にとってリスクが軽減されるため、プロパー融資(金融機関が保証協会なしで直接融資すること)が難しい開業時でも、融資を受けられる可能性が高くなります。
3)制度融資
制度融資は、地方自治体(都道府県や市区町村)と信用保証協会、そして金融機関が連携して提供する融資制度であり、その多くは信用保証協会付き融資の枠組みを利用しています。地方自治体が金利の一部を負担するなど、起業家への支援策が上乗せされている点が特長です。
自治体の事業支援の一環として実施されているため、地域経済への貢献度が高いと判断されれば、より融資を受けやすくなる可能性があります。基本的には信用保証協会付き融資の一種ですが、地方自治体で専門家との事前相談が行われることが多く、金融機関の審査における信頼性が増す効果が期待できる場合もあります。
3.開業資金の融資で金融機関を選ぶ際の注意点
開業資金の融資では、融資を受けやすい金融機関を選ぶだけでは足りません。選択の際には、いくつか重要な注意点が存在します。とくに、創業期の事業に対する姿勢や、融資制度の特性を理解しておくことが、円滑な資金調達への鍵となります。
1)日本公庫以外なら信用金庫がよい
前述の日本公庫を除き、開業融資の相談先として現実的なのは信用金庫です。信用金庫は地域密着型で、大手の銀行と比較して、小規模な事業者や新規事業にも親身になって相談に乗ってくれる傾向があります。
事業計画の細かな部分まで耳を傾け、地域の活性化という観点からも支援を検討してくれるケースが多いため、まずは地元の信用金庫に足を運んでみることを推奨します。
2)プロパー融資はほぼ難しい
開業時において、信用保証協会の保証のないプロパー融資を受けることは、ほぼ不可能だと認識しておくべきです。これは、開業時にはまだ企業の信用力がないためです。実績のない新規事業に対して、金融機関が単独で大きなリスクを負うことは稀であるため、開業融資を考える際は、最初から日本公庫の融資制度か、信用保証協会付き融資をメインの選択肢として検討を進めることが賢明です。
3)メガバンクから開業融資を受ける必要なし
メガバンクから開業融資を受けられる必要性は極めて低いです。メガバンクは取引先の規模や実績を重視するため、創業間もない小規模事業者に対する融資には消極的であり、親身になって相談に乗ってくれることは期待できません。
また、そもそも開業時の事業者のメインバンクになることは稀であり、口座開設じたいが難しいケースすらあります。開業融資の目的は、事業を軌道に乗せるための資金調達であり、金融機関のブランド力にこだわる必要はありません。
4)ビジネスローンは金利が高いので注意
手軽に借入れできるイメージがあるビジネスローンですが、これは開業融資の選択肢としては避けるべきです。ビジネスローンは、一般的な銀行融資と比較して金利が非常に高く設定されており、事業の初期段階で高い金利負担を負うことは、資金繰りを圧迫し、事業継続の大きな足枷となり得ます。緊急時や少額のつなぎ資金としては有効な場合もありますが、本格的な開業資金としては不向きであることを理解しておく必要があります。
5)補助金や助成金も検討する
融資に加えて、返済不要の資金として補助金や助成金も同時に検討することも有効です。これらは国や地方自治体が提供するもので、新規事業の立ち上げを支援する目的で実施されています。融資と異なり、原則として返済の必要がないため、積極的に活用すべきですが、公募期間が限定されており、申請に専門的な知識が必要な場合もあるため、常に最新情報を収集し、必要に応じて専門家のサポートを受けることをおすすめいたします。
- 累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる
- 12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定
4.開業資金で利用できる日本政策金融公庫の制度
前述のとおり、日本政策金融公庫は開業融資の強力な選択肢であり、起業家の状況に応じた複数の制度を提供しています。これらの制度を理解し、自身の事業計画にもっとも適したものを選ぶことが成功への近道となります。
1)新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)
この制度は、女性、35歳未満の若者、または55歳以上のシニア層の起業家を対象とした支援策です。これまでの実績や経験、事業の将来性を総合的に評価し、通常よりも有利な条件で融資を受けられる可能性があります。該当する起業家は積極的に利用を検討すべき制度です。
参考:新規開業・スタートアップ支援資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)
2)新規開業資金(再挑戦支援関連)
過去に事業に失敗した経験があるものの、その経験を活かして再度事業に挑戦しようとする方を支援するための制度です。過去の失敗を教訓とし、具体的な改善策や再チャレンジへの熱意を明確に示すことが融資成功の鍵となります。
3)新規開業資金(中小企業経営力強化関連)
「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」が適用されている、または適用される予定である場合に利用できる制度です。認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けることも必要となりますが、条件に該当する場合には利用を検討する価値があります。
参考:新規開業・スタートアップ支援資金(中小企業経営力強化関連)
5.開業資金の融資を成功させるためのポイント
開業融資の審査を通過するためには、金融機関が重視するポイントを理解し、それに基づいた準備を進めることが不可欠です。単に資金を借りるという行為ではなく、事業の実現性と返済能力を金融機関に納得させるためのプロセスと捉えるべきです。
1)業種によるが500~1,000万円が目安
融資の希望額は、事業の規模や業種によって異なりますが、開業時における融資の目安として500万円から1,000万円程度がひとつの基準となります。この金額は、金融機関が新規事業に対して比較的融資しやすいとされる範囲です。それ以上の高額な融資を希望する場合、自己資金の比率を大幅に高めるなど、より強固な財務基盤と明確な返済計画が求められることを認識しておくべきです。
参考:日本政策金融公庫総合研究所「2024年度新規開業実態調査」
2)開業前~開業後3カ月以内に申請する
融資申請のタイミングは非常に重要です。金融機関は開業前や開業直後の事業に対しては、実績ではなく、将来性や熱意を評価する傾向があります。しかし、開業後しばらく経ってしまうと、じっさいの実績(売上や利益)で評価されることになります。そのため、開業前か開業直後でまだ実績が少ない開業後3カ月以内に申請をおこなうのがもっとも有利なタイミングとなるでしょう。この時期であれば、まだ事業計画の将来性が重視されやすいからです。
3)開業業種の経験を提示する
開業時の融資審査では、実績がない分、起業家の経歴が極めて重視されます。とくに、これからはじめる事業と同業種での実務経験を提示できることは、事業の実現性、つまり「この人ならこの事業を成功させられるだろう」という金融機関からの信頼感獲得につながります。具体的な経験年数や成果を事業計画書に明記し、専門性と経験値を強調することが成功への重要なポイントです。
4)自己資金比率を高める
自己資金(返済の必要がない自分で用意した資金)の比率は、金融機関が融資の可否を判断するうえでもっとも重視する項目のひとつです。一般的には、総事業費に対する自己資金の比率を30%以上にすることが望ましいとされています。自己資金が多いほど、起業家の事業に対する本気度が高く、また事業が困難に直面した際の耐久力があると評価されるため、可能な限り自己資金を積み立てておくべきでしょう。
参考:「自己資金は3割必要」ってホント!?元・銀行支店長が教える、創業融資の必勝法②資金計画
5)信用情報の傷があれば回復させる
過去に公共料金や税金、クレジットカード、ローンの支払いに遅延があった場合、それらは信用情報に「傷」として残り、融資審査において極めて不利に働きます。金融機関は返済能力と信用度を厳しく審査するため、心当たりのある方は、融資申請の前にこれらの問題を完全に解消し、信用情報の回復に努めることが、融資成功のための大前提となります。
- 累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる
- 12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定
6.事業計画書作成サポートツールで成功率アップ!
開業融資の審査において、事業計画書はあなたの事業の「顔」であり、審査担当者に事業の実現性と返済能力を伝える唯一の文書です。この事業計画書の完成度こそが、融資の成功率を大きく左右するといっても過言ではありません。
融資のプロの視点からいえば、多くの方が自己流で作成し、金融機関が求める形式や論理構成を満たせていないケースが散見されます。そこで活用を推奨したいのが、専門的な知見に基づいた事業計画書作成サポートツールです。
とくにドリームゲートが提供している「事業計画書作成サポートツール」は、金融機関の視点を踏まえた構成になっており、はじめての方でも説得力のある事業計画書を作成できるよう設計されています。このツールを活用し、事業計画の精度を高めることが、融資成功への確実な一歩となるでしょう。
- 累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる
- 12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定

元日本政策金融公庫の融資課長として5000名以上の起業家を支援した上野アドバイザー。現在は、資金調達の専門家として活躍されております。融資を検討されている方はぜひご相談ください。
著書「事業計画書は1枚にまとめなさい」「起業は1冊のノートから始めなさい」など。
プロフィールを見る>>