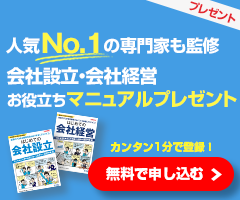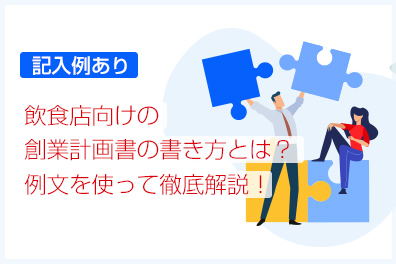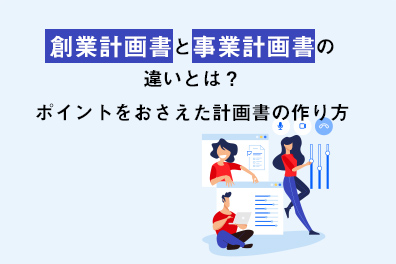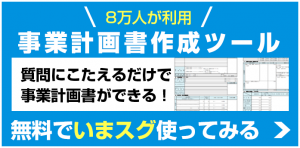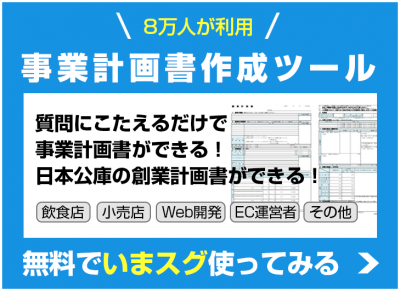農業の事業計画書の書き方・記入例をテンプレを基に融資のプロが解説
新規就農や農業での事業拡大を目指す際、事業計画書は単なる書類作成作業ではなく、事業の成功確率を高めるための「設計図」となります。また、金融機関からの融資や補助金を受ける際には、その事業の実現性、収益性、そして将来性を示す重要なツールともなります。
そこで本記事では、融資のプロの視点から、農業特有の要素を踏まえつつ、実践的な事業計画書の書き方と、参考にすべきテンプレートをわかりやすく解説します。この解説を基に、説得力のある事業計画書を作成し、理想の農業経営を実現する一歩を踏み出しましょう。
8万人が利用した事業計画書作成ツール
ブラウザ上の操作で事業計画を作成、創業計画書もエクセルでダウンロード可能
元日本政策金融公庫の融資課長として5000名以上の起業家を支援した上野アドバイザー。現在は、資金調達の専門家として活躍されております。融資を検討されている方はぜひご相談ください。
著書「事業計画書は1枚にまとめなさい」「起業は1冊のノートから始めなさい」など。
プロフィールを見る>>

目次
1.そもそも事業計画書とは
事業計画書とは、これからはじめようとする、あるいはすでに実施している事業の内容、具体的な戦略、資金計画、そして将来的な見通しなどを明確に文書化したものです。絶対的なフォーマットが存在するわけではありませんが、金融機関や出資者に事業の「説得力」を示すためのもっとも重要な資料であることは間違いありません。事業主自身にとっても、計画を具体化し、課題やリスクを事前に洗い出すための思考整理のツールとして極めて有効です。
創業期に作成する事業計画書は、日本政策金融公庫などの融資制度においては「創業計画書」と呼ばれることも多く、主に新規開業者や開業間もない事業者が利用するものです。効果的な事業計画書を作成するためには、読み手が事業全体を容易に理解でき、その将来性に確信を持てるような論理的かつ具体的な記述をおこなうことが重要です。
2.農業の事業計画書の書き方
農業の事業計画書も、一般的な創業計画書と同様に、事業主の経歴から資金計画、そして具体的な事業の見通しまで多岐にわたる項目で構成されます。
ここでは、主要な構成要素とその書き方について、ポイントをおさえながら具体的に解説していきます。各項目を有機的に関連付け、一貫性のあるストーリーとして提示することが、金融機関の信頼をえるうえで不可欠な要素となります。
参考:事業計画書の実例が無料で見れる!実例から事業計画書の書き方を習得しよう
1)創業の動機・目的
農業をはじめるにいたった動機や、地域や品目を選んだ理由といった、事業の根幹となる思いとビジョンを記述する部分です。単なる憧れや漠然とした希望ではなく、「この地域で求められている作物を安定供給したい」「独自の販路を開拓し、高付加価値な農業を実現したい」といった、具体的な課題解決や事業の優位性に結びつく動機を明確にすることが重要です。この項目は、事業主の熱意と事業の軸を示すため、融資の審査においても非常に重視されます。
2)職歴・事業実績
事業主のこれまでの経歴や、農業に関する経験・スキルを具体的に記載します。新規就農の場合は、農業研修の期間や内容、取得した資格、異業種での管理経験などを詳述することで、事業を遂行できる能力と、培ってきたノウハウの裏付けをおこないます。
すでに事業をおこなっている場合は、これまでの実績(売上高、利益率、栽培成果など)を定量的に示し、計画の実現可能性を高めるための根拠とします。
- 累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる
- 12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定
3)取り扱い商品・サービス
ここで具体的にどのような農産物(作物名、品種、規格)やサービス(加工品、体験観光など)を提供するかを明記します。単に「野菜」と書くだけでなく、「高糖度トマトA品種を年間〇トン生産し、規格外品は主に自社で加工して販売する」といった詳細な情報が必要です。商品の差別化ポイントや、ターゲットとする顧客層にとっての価値を明確にすることで、市場における優位性を示すことができます。
4)取引先・取引関係
生産した作物をどこに販売するか、種苗や資材をどこから仕入れるかといった、事業を取り巻く主要な取引関係を記載します。具体的な販売先(市場、スーパー、直売所、レストラン、ECサイトなど)とその取引条件、さらには取引予定の有無を明確にすることで、事業の安定性や収益構造の信頼性が高まります。契約栽培や大口の取引先がすでに決まっている場合は、その証拠を添付することで計画の確実性が増すでしょう。
5)従業員
事業を支える従業員の構成と計画を記述します。正社員、パート・アルバイトの人数、それぞれの役割分担、そして人件費計画を具体的に示します。家族従業員がいる場合は、その役割も明記しましょう。農業経営においては労働力の確保が重要な課題となるため、とくに大規模経営を目指す場合、適切な労働環境と賃金設定に基づく人材採用・育成計画の有無が評価対象となります。
6)借入の状況
現在借入れている資金(住宅ローンやそのほかの借入金など)の残高、借入先、返済状況などを正確に記載します。この項目は、事業主の信用情報と返済能力を金融機関が把握するために必要となります。正確な情報を開示することが、新たな融資審査における信頼構築の土台となるでしょう。
7)必要な資金と調達方法
事業開始・継続に必要な資金の総額を、設備投資(農機具、施設など)、運転資金(種苗、肥料、人件費、燃料費など)に分けて詳細に算出します。そのうえで、自己資金、親族からの借入、金融機関からの融資など、資金の調達源を具体的に示しましょう。融資を希望する場合は、借入希望額とその使途を明確にすることで、資金計画の妥当性を示します。
8)事業の見通し・市場戦略
生産計画と販売戦略に基づいた具体的な収益見通しを、過去1~2年分と今後3~5年程度の期間で作成します。売上高、売上原価(費用)、利益(損益計算書)を月別や年別に示すことによって、事業の採算性と成長性を論理的に裏付けることが求められます。市場の状況、競合との差別化戦略、目標とする売上高の根拠などを明確に記載することで、計画の実現可能性を強調することが可能です。
3.農業の事業計画書を書くうえでのポイント
農業の事業計画書は、一般的なビジネスと異なり、天候や土壌といった自然条件、さらには市場価格の変動といった特有のリスク要因がともないます。そのため、これらの特殊な要素を計画に織り込み、実現可能性を高めることが極めて重要です。とくに次の3つのポイントを重点的に記述し、事業の確実性を裏付けるべきです。
1)生産計画(作物・技術・労働力)
「何を」「どの規模で」「どのような方法によって」つくるのかを示すこの部分は、農業経営の根幹です。農業は、天候や土壌条件に事業成果が強く依存するため、「この品目を選んだ根拠(例:地域の特産品としての需要、他産地との時期のずれによる優位性など)」や、「具体的な栽培技術(例:環境制御技術の導入、有機農法の採用など)」を具体的に示し、品質と収量の安定化に向けた戦略を明記することが重要です。さらに、農繁期・農閑期に応じた労働力の確保計画を具体化することで、生産能力の裏付けをおこないましょう。
2)販売戦略(販路・需要・価格)
生産した作物を「どう売るか」を明確にすることは、安定した収益確保に直結します。市場出荷、農協、直売所、EC販売、契約栽培など、複数の販路を選択する際のメリット・デメリットを比較し、ターゲット顧客に合わせた最適な販路構成を示すべきです。また、競合との比較に基づいた価格設定の妥当性や、需要変動への対応策を整理することで、事業の持続性を論理的に裏付けられます。
3)リスク管理(自然・経営・価格変動)
農業特有のリスクとして、天候不順、病害虫の発生、市場価格の変動は避けて通れません。これらのリスクに対する備えを計画書に明記することが、金融機関に対して高い危機管理能力を示すことになります。具体的には、農業共済や民間保険への加入、複数品目の栽培によるリスク分散、契約栽培による価格変動のヘッジ、さらには緊急時のための十分な運転資金の確保といった、リスクを最小限におさえるための具体的なしくみを明示する必要があります。
4.事業計画書のテンプレート集
説得力のある事業計画書を作成するためには、雛形(テンプレート)を参考にし、必要な項目を漏れなく記述することが効率的です。公的機関や専門家が提供するテンプレートは、金融機関の審査基準や事業計画に必要な構成要素を満たすように作られているため、はじめて作成する方にとって非常に役立ちます。以下に、農業経営者におすすめの代表的なテンプレートを紹介します。
1)日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は、創業期の融資において広く利用されており、その提供する「事業計画書」はもっとも汎用性の高いテンプレートのひとつです。幅広い業種に対応しており、融資の申込みを検討している場合は、この様式を基に作成することがもっとも適切でしょう。
なお、日本政策金融公庫の「農林水産事業」では「新たな農業経営の開始」向けの融資制度がありますのでそちらもチェックしてみてください。
2)J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営するJ-Net21では、事業計画書や創業計画書の作成マニュアルとテンプレートを提供しています。体系的な事業計画の立て方について詳細な解説があるため、計画を具体化する際の思考プロセスを整理するうえで大変参考になります。
参考:事業計画書の作成例
3)ドリームゲート
起業家支援のプラットフォームであるドリームゲートも、さまざまな業種に対応した事業計画書のテンプレートを提供しています。実務家の視点から、収益性や市場戦略の記述に役立つ項目が盛り込まれており、より実践的な計画書を作成したい場合に有用です。
参考:資金調達に成功した『事業計画書』11業種12社の見本をダウンロード
5.農業の事業計画書作成はドリームゲート
事業計画書の作成は、融資の成否や事業の将来を左右する重要なプロセスです。しかし、はじめて作成する方や専門的な視点を取り入れたい方にとっては、どのテンプレートを選び、どう具体的に記述すべきか悩むこともあるでしょう。
そのような場合には、ドリームゲートの事業計画書作成サポートツールを利用することで、緻密な計画策定が可能です。とくに、成功した経営者のデータを活用できる点は、農業経営特有のリスクや収益性を織り込んだ、説得力のある事業計画書へと昇華させるための強力な助けとなるでしょう。無料で使えますので、まずは試してみることをおすすめします。
- 累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる
- 12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定

元日本政策金融公庫の融資課長として5000名以上の起業家を支援した上野アドバイザー。現在は、資金調達の専門家として活躍されております。融資を検討されている方はぜひご相談ください。
著書「事業計画書は1枚にまとめなさい」「起業は1冊のノートから始めなさい」など。
プロフィールを見る>>