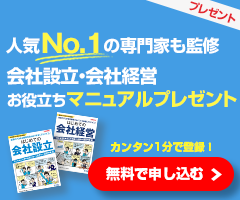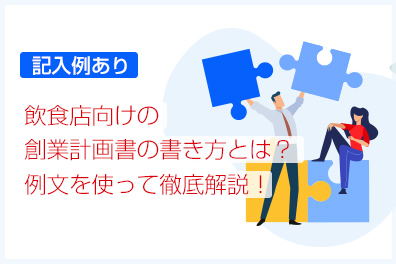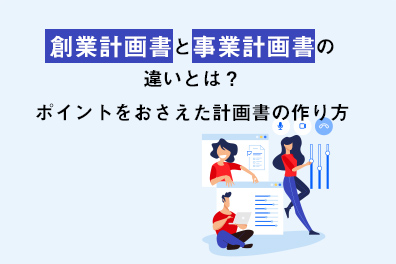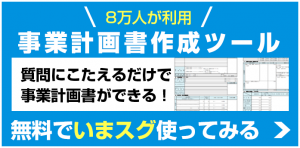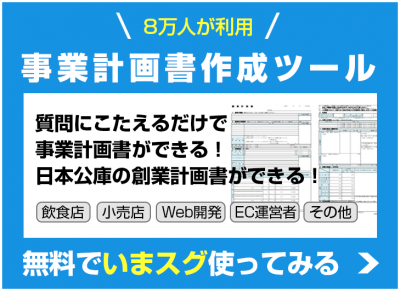クリニックの成功に必要な開業資金の目安を創業融資のプロが徹底解説
クリニックの開業は多くの医師にとっての夢であり、大きなキャリアステップです。しかし、その道のりは決して平坦ではありません。とくに、開業資金の準備は成功を左右する重要な要素となります。
そこで本記事では、創業融資の専門家としての知見を活かし、クリニック開業に必要な資金の全体像、内訳、診療科目別の目安、そして効果的な資金調達方法まで、網羅的に解説していきます。これから開業を目指す方々が、現実的で堅実な事業計画を立てるための羅針盤となることを目指します。
8万人が利用した事業計画書作成ツール
ブラウザ上の操作で事業計画を作成、創業計画書もエクセルでダウンロード可能
元日本政策金融公庫の融資課長として5000名以上の起業家を支援した上野アドバイザー。現在は、資金調達の専門家として活躍されております。融資を検討されている方はぜひご相談ください。
著書「事業計画書は1枚にまとめなさい」「起業は1冊のノートから始めなさい」など。
プロフィールを見る>>

目次
1. そもそも開業資金とは
開業資金とは、事業を開始し、軌道に乗せるために必要となるすべての費用を指します。一般的に「運転資金」「設備資金」「法人設立費用」の3つの要素に大別できます。
これらの資金は、事業の規模や業種によって大きく変動するため、正確な見積もりと計画が不可欠です。とくにクリニックの開業においては、高額な医療機器や内装工事費が資金の大部分をしめるため、入念なシミュレーションが求められます。
1)運転資金
運転資金は、事業の日常的な運営に必要となる資金です。具体的には、人件費、家賃、水道光熱費、広告宣伝費、消耗品費などが含まれます。事業開始当初は、予測していたよりも多くの費用が発生する可能性があるため、余裕を持った資金計画が重要です。
参考:創業融資の運転資金は何か月分が妥当か?【元日本公庫融資課長が監修】
2)設備資金
クリニックの事業活動に不可欠な、長期的に利用する設備や備品を購入するための資金です。診察台、医療機器、検査機器、医療用ソフトウェアなどが該当します。とくにクリニックの場合、高額なMRIやCTスキャンなどの設備投資が必要となることがあり、この費用が全体の資金計画に大きな影響を与えるため注意が必要です。
3)法人設立費用
個人事業主ではなく、法人としてクリニックを開設する場合にかかる資金です。具体的には、定款認証費用、登録免許税、司法書士への報酬などが含まれます。これらの費用は比較的少額ですが、開業資金全体の計画を立てるうえで見落とされがちな項目です。
- 累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる
- 12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定
2. クリニックの開業資金はいくら必要か
クリニックの開業には、一般的な事業と比較して非常に多額の資金が必要になります。事業計画の初期段階で、具体的な費用を算出し、資金調達の目処を立てることが成功への第一歩となるでしょう。ここでは、クリニック開業資金の目安と、その内訳についてくわしく解説していきます。
1)目安は5,000万~2億円程度
クリニックの開業資金は、一般的に5,000万円から2億円程度が目安とされています。これは、診療科目の専門性、導入する医療機器の種類、立地条件、内装の規模などによって大きく変動する金額です。
都市部の一等地に最新の設備を備えた大規模なクリニックを開業する場合、1億円を超えることも珍しくありません。一方、地方都市で小規模なクリニックを開業する場合や、既存クリニックを買収して開業する場合などは、5,000万円以下におさえられることもあり得ます。
2)クリニック開業資金の費用内訳
クリニックの開業資金は、多岐にわたる項目で構成されています。
敷金・礼金
物件を借りる際に支払う費用で、家賃の数カ月分が一般的です。
仲介手数料
不動産仲介会社に支払う手数料です。
前家賃
開業前の数カ月分の家賃を前払いする場合があります。
内装工事費
医療機関としての機能を持たせるための内装工事費用です。
診療設備費
診察台、X線装置、心電計など、診療に不可欠な設備です。
医療機器購入/リース費
高額な医療機器を導入する場合の費用です。
什器費
診察室や待合室のデスク、椅子、棚などの購入費用です。
OA機器購入費
パソコン、プリンター、レジなどの購入費用です。
消耗品費
注射器、ガーゼ、薬品などの初期在庫費用です。
集患・広告費
開業告知のチラシ、ホームページ制作、看板設置費用などです。
採用・研修費
医師、看護師、医療事務スタッフなどの採用と研修にかかる費用です。
医師会諸経費
入会金や年会費などの費用です。
そのほか備品費
電子カルテ導入費用、事務用品、清掃用具、ユニフォームなどです。
固定費(賃料・人件費)など
開業後の数カ月分の運転資金として確保しておく費用です。
3. 診療科目別の開業資金の目安
クリニックの開業資金は、診療科目によって大きく変動します。とくに、専門的な医療機器の導入が必要な診療科では、開業資金が高額になる傾向があります。ここでは、主な診療科目別に開業資金の目安を解説します。
1)内科
内科には、一般内科、一般内科
、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、内分泌、糖尿病内科などがあります。
開業資金の目安は5,000万〜1億円万円程度です。レントゲン、心電図、超音波診断装置など、基本的な検査機器の導入が中心となります。幅広い疾患に対応するため、多様な消耗品や薬品が必要になります。科目によっては、肺機能検査装置、気管支鏡検査装置、心臓超音波診断装置、上部・下部消化管内視鏡など、より専門的な機器の導入が必要です。
2)整形外科
開業資金の目安は6,000万〜1.5億円程度です。レントゲン撮影装置、MRI、CTスキャン、骨密度測定装置など、高額な画像診断機器が必要となります。
3)耳鼻咽喉科
開業資金の目安は5,000万〜1億万円程度です。聴力検査室の防音工事、顕微鏡、聴力検査装置など、特殊な設備が必要となります。
4)眼科
開業資金の目安は7,000万〜1.2億円程度です。視力検査装置、眼圧計、網膜眼底検査装置、手術用顕微鏡など、専門性の高い機器が多いため、開業資金が高額になりやすい傾向にあります。
5)皮膚科
開業資金の目安は4,000万〜7,000万円程度です。内科の設備に加え、皮膚科用のレーザー治療器や紫外線治療器などを導入する場合、費用はさらに増加します。
6)精神科・心療内科
開業資金の目安は3,500万〜5,000万円程度です。特別な医療機器がほとんど必要ないため、ほかの診療科に比べて開業資金をおさえやすいのが特徴です。
7)泌尿器科
開業資金の目安は5,000万〜1億円程度です。超音波診断装置、膀胱鏡、尿流量測定装置などが必要となります。
8)脳神経外科・内科
開業資金の目安は1億円〜2億円程度です。CT、MRIなどの画像診断機器、脳波計など高額な医療機器が必要となります。
9)小児科
開業資金の目安は4,500万〜8,000万円程度です。レントゲン、超音波診断装置など、一般的な内科設備に加え、予防接種用の薬品や乳幼児向けの待合室設備などが必要となります。
10)産科・婦人科
開業資金の目安は7,000万〜2億円程度です。超音波診断装置、分娩台、胎児心拍数モニター、手術室設備など、高額な専門機器が多いため、開業資金が高額になりやすいです。
11)歯科
開業資金の目安は5,000万円 ~ 1億円程度です。歯科ユニット、レントゲン・CT、バキューム・コンプレッサーなどの専門機器が必要です。
- 累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる
- 12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定
4. クリニックの開業資金の調達方法
クリニック開業に必要な多額の資金を、すべて自己資金でまかなうことは現実的ではありません。多くの医師は、金融機関からの融資や補助金・助成金などを組み合わせて資金を調達します。ここでは、代表的な資金調達方法について解説します。
1)日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は、政府系金融機関であり、開業医向けの融資制度を設けています。民間金融機関よりも低金利で、長期の返済期間を設定できるのが特徴です。実績がなくても融資を受けやすい傾向にあり、開業を検討している医師にとって心強い味方となります。
2)独立行政法人福祉医療機構
独立行政法人福祉医療機構(WAM)は、福祉・医療事業の振興を目的とした政府系機関です。クリニックの新規開業や既存施設の改修に対する融資制度を提供しています。日本政策金融公庫と同様に、比較的低金利で融資を受けることが可能です。
3)民間金融機関
銀行や信用金庫などの民間金融機関も、クリニック開業向けの融資商品を提供しています。日本政策金融公庫や福祉医療機構と比べて、審査がきびしい傾向にありますが、柔軟な融資プランを提案してもらえる可能性があります。
4)補助金と助成金
国や地方自治体は、特定の条件を満たす事業に対して、返済不要の補助金や助成金を提供しています。たとえば、医療機器の導入やIT化に関する補助金などがあります。これらの情報は常に変化するため、最新の情報を確認することが大切です。
5)リース会社
高額な医療機器は、リース会社を利用して導入することも可能です。リースは、機器を自社で購入するのではなく、リース会社から借りて使用するしくみです。初期費用をおさえられる利点がありますが、長期的に見ると購入よりも総支払額が高くなる場合があります。
5. 開業資金の融資を成功させるポイント
クリニック開業の成功は、適切な資金調達にかかっています。ここでは、金融機関からの融資を成功させるための重要なポイントを3つ解説します。これらのポイントをおさえることで、融資審査の通過率を高めることができるでしょう。
1)自己資金比率を高める
金融機関は、自己資金の割合を重視し、一般的に、総必要金額の30%以上の自己資金を準備することが理想とされています。自己資金が多いほど、経営者の熱意や返済能力が高いと判断され、融資審査に有利に働きます。
2)開業前〜開業3カ月以内に申請する
融資の申請は、開業前または開業後3カ月以内におこなうのが理想的です。開業後しばらく時間が経ってしまうと、金融機関はクリニックの経営実績をきびしく見るようになります。まだ実績がない段階の方が、事業計画の将来性や医師の経歴を評価して融資が承認されやすい傾向があります。
3)税理士・中小企業診断士から金融機関を紹介してもらう
開業資金の調達においてもっとも重要な要素のひとつが、信頼できる税理士の存在です。税理士・中小企業診断士は、金融機関とのネットワークを持っているため、個々の事業計画に合った最適な金融機関を紹介してくれます。また、事業計画書の作成をサポートしてもらうことで、説得力のある資料を作成することができ、融資の成功率が格段に高まります。
6. 事業計画書作成サポートツールで成功率アップ!
クリニックの開業は、事業計画書を作成するところから始まります。しかし、事業計画書の作成は多くの医師にとって慣れない作業であり、専門的な知識も必要とします。そこで活用したいのが、事業計画書作成サポートツールです。
ドリームゲートの事業計画書作成サポートツールは、専門家の知見が詰まったツールであり、事業計画書の作成をスムーズに進めることができます。このツールを活用することで、資金調達の成功率を高め、クリニックの成功を確かなものにできるでしょう。
- 累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる
- 12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定

元日本政策金融公庫の融資課長として5000名以上の起業家を支援した上野アドバイザー。現在は、資金調達の専門家として活躍されております。融資を検討されている方はぜひご相談ください。
著書「事業計画書は1枚にまとめなさい」「起業は1冊のノートから始めなさい」など。
プロフィールを見る>>