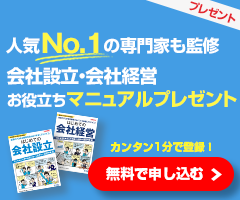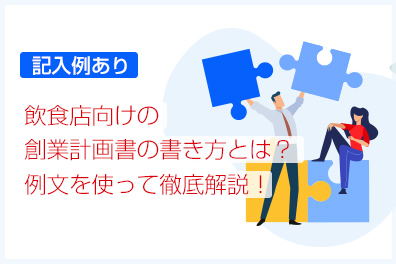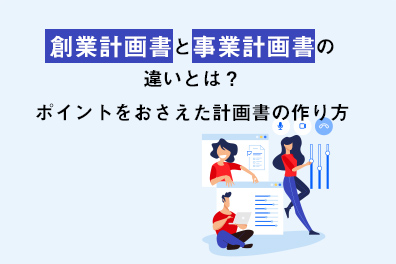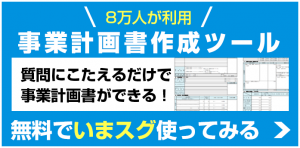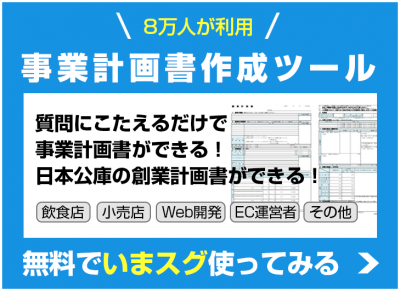バーを成功させるのに必要な開業資金はいくら?創業融資のプロが解説
飲食店やバーで働いていると、「いつか自分のお店を持ちたい」と思う人はいると思います。しかし、夢の実現には適切な準備が不可欠であり、なかでも開業資金の確保は最も重要な課題といえます。どれくらいの資金が必要なのか、どのように調達すればよいのか、不安に感じている方も多いはずです。
そこで本記事では、創業融資の専門家が、バー開業に必要な資金の全体像から、融資を成功させるための具体的なノウハウ、さらに開業に必要な手続きまでを徹底解説します。本記事が、あなたのバー開業という夢を、現実のものとするための羅針盤となることを願っています。
8万人が利用した事業計画書作成ツール
ブラウザ上の操作で事業計画を作成、創業計画書もエクセルでダウンロード可能
元日本政策金融公庫の融資課長として5000名以上の起業家を支援した上野アドバイザー。現在は、資金調達の専門家として活躍されております。融資を検討されている方はぜひご相談ください。
著書「事業計画書は1枚にまとめなさい」「起業は1冊のノートから始めなさい」など。
プロフィールを見る>>

目次
1.そもそも開業資金とは
開業資金とは、事業をはじめるために必要なすべての費用のことを指し、大きく設備資金と運転資金の2つに分けられます。
一般的に、バーのような飲食業では、店舗の賃貸契約から内装工事、厨房設備の導入、さらには開業後の運転費用まで、多岐にわたる資金が必要となります。これらの資金は、事業を円滑に立ち上げ、安定して経営を続けるために欠かせないものです。
1)運転資金
運転資金とは、事業開始後に発生する日常的な費用、いわゆるランニングコストのことです。具体的には、人件費、家賃、水道光熱費、食材や酒類の仕入れ費用、広告宣伝費などが含まれます。
バー経営では、とくに初期の売上が不安定な時期に、これらの費用を賄うための余裕資金を確保しておくことが極めて重要となります。事業計画を立てる際には、最低でも3ヶ月から6ヶ月分の運転資金を確保しておくことが推奨されます。
参考:創業融資の運転資金は何か月分が妥当か?【元日本公庫融資課長が監修】
2)設備資金
設備資金とは、事業をおこなうために必要な設備や什器、備品などを購入する費用です。バーの場合、カウンター、テーブル、椅子といった客席周りの備品、グラスやカクテルシェーカーなどのバーツール、冷蔵庫や製氷機、シンクなどの厨房設備、さらには音響設備や照明器具などが該当します。内装工事費用もこの設備資金に含めて考えるのが一般的です。
3)法人設立費用
個人事業主として開業する場合は不要ですが、法人として開業する場合には、法人の設立登記にかかる費用が発生します。定款認証費用、登録免許税、司法書士への報酬などがこれにあたります。将来的に事業規模を拡大したい、あるいは対外的な信用力を高めたいといった目的がある場合には、法人設立も検討する価値があるでしょう。
- 累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる
- 12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定
2.バーの開業資金はいくら必要か
バーの開業に必要な資金は、立地や店舗の規模、コンセプトによって大きく変動します。たとえば、個人で小規模なバーを開業する場合と、大規模なダイニングバーを開業する場合とでは、当然ながら必要な資金も大きく異なってきます。
1)500万~1,000万円程度が目安
バーの開業に必要な資金は、一般的に500万円から1,000万円程度がひとつの目安となります。もちろん、これはあくまでも平均的な金額であり、物件の取得費用や内装工事の規模、備品や設備へのこだわりによって、この金額は上下します。
たとえば、居抜き物件を活用して初期費用を抑えたり、DIYで内装の一部を自分で行ったりすれば、より少ない資金で開業することも不可能ではありません。逆に、一から内装を造り込むスケルトン物件で、質の高い内装や音響設備にこだわれば、2,000万円以上かかることも珍しくありません。
2)費用内訳
バーの開業資金は、複数の項目で構成されています。それぞれの項目を具体的に見ていきましょう。
①物件取得・賃貸契約
バーの立地は成功を左右する重要な要素です。賃貸契約時には、通常、敷金・礼金、仲介手数料、前家賃などがかかります。これらは、一般的に家賃の6ヶ月分程度に相当することが多いです。
②内装工事
店舗の雰囲気を決める内装工事は、バーのコンセプトを体現するうえで最も重要な部分のひとつです。照明、カウンター、壁や床の素材など、細部にまでこだわり、理想の空間を創り出すための費用となります。
③厨房設備
製氷機、冷蔵庫、シンク、食洗機など、バーの営業に不可欠な厨房設備です。どのようなメニューを提供するかに応じて必要な設備は変わってきます。
④家具・備品
客席のテーブルや椅子、カウンターチェア、グラス、カクテルシェーカーなどのバーツール、カトラリーなど、営業に必要な家具や細かな備品です。
⑤初期在庫
開業当初のメニュー提供に必要な酒類やソフトドリンク、食材などを仕入れるための費用です。
⑥広告宣伝費
開業を告知し、集客を促すための費用です。SNS広告、チラシ作成、ウェブサイト制作などが含まれます。
⑦開業諸経費
火災保険料、名刺作成費、電話回線やインターネット回線の敷設費用など、上記以外の雑多な費用です。
⑧運転資金
開業後、軌道に乗るまでの運転費用です。家賃、人件費、仕入れ費、水道光熱費など、最低でも3ヶ月分から6ヶ月分は確保しておきたいところです。
3)バーはコンセプトによって必要資金額が左右する
バーの開業資金は、どのようなバーを目指すかによって大きく変わります。たとえば、ショットバーのようにドリンク提供が中心で、フードはかんたんな軽食のみとするコンセプトであれば、厨房設備は最小限で済み、初期費用を抑えられます。
一方、ダイニングバーのように本格的な料理も提供するとなれば、厨房設備への投資が不可欠となり、開業資金は必然的に高くなります。また、高級志向のオーセンティックバーでは、内装や備品にこだわるため、資金も多く必要となるでしょう。
3.バーの開業資金の調達方法
バー開業にあたり、自己資金だけでは不足する場合がほとんどです。その際には、外部からの資金調達を検討する必要があります。
1)日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は、政府が100%出資する金融機関であり、創業支援に積極的です。民間の金融機関よりも低金利で融資を受けられる可能性が高く、とくに実績のない創業者にとって最も現実的な選択肢といえるでしょう。創業融資を検討する際には、まずは最初に日本政策金融公庫に相談するべきです。
2)民間金融機関
信用金庫や地方銀行といった民間の金融機関も、開業資金の融資をおこなっています。しかし、創業実績がない場合、無担保・無保証での融資は難しく、一般的には信用保証協会の保証を付けることで融資を受けやすくなります。とくに、規模の小さいバーや飲食店の場合、信用保証協会付きの信用金庫融資が現実的な選択肢となるでしょう。
参考:創業融資における信用保証協会の役割とは?|資金調達のプロが公庫と徹底比較
3)補助金と助成金
国や地方自治体は、特定の要件を満たす事業に対して、返済不要の補助金や助成金を提供しています。これらは返済の必要がないため、積極的に活用したいところです。ただし、申請期間が限られていたり、審査に時間がかかったりするため、計画的に準備を進める必要があります。
- 累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる
- 12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定
4.バーの開業資金の融資を成功させるコツ
創業融資を成功させるためには、金融機関が「この人に融資をしても大丈夫だ」と判断できるような説得力のある事業計画を提示する必要があります。以下に、そのための具体的なコツを5つ紹介します。
1)独自の強みを強調する
バー業界は競合が多く、成功するためには他店との差別化が不可欠です。融資の際には、店舗のコンセプトやターゲット、独自の強みなどを明確に伝えることが重要となります。
2)開業業種の経験を提示する
バーは未経験者でも開業可能ですが、実は飲食店勤務経験があるかどうかが融資の審査に大きく影響します。とくにバーでの勤務経験があれば、経営者としての資質や業界への理解度を示すことができ、金融機関からの信用を得やすくなります。
3)自己資金比率を高める
自己資金比率とは、総必要金額に占める自己資金の割合のことです。この比率が高いほど、経営者の本気度や事業への熱意が伝わり、融資審査において有利に働きます。一般的には、総必要金額の3分の1から、半分程度の自己資金を用意することが推奨されます。
4)開業前〜開業3ヶ月以内に申請する
開業直後や開業後間もない時期は、事業の軌道修正がしやすく、融資の目的も明確であるため、金融機関としても融資の判断がしやすい時期です。このタイミングで申請することで、融資の成功率を高められるでしょう。
5)税理士や中小企業診断士から金融機関を紹介してもらう
創業融資に強い税理士や中小企業診断士は、融資のポイントを熟知しています。彼らが金融機関と日ごろから築いている信頼関係を活用することで、融資審査をスムーズに進められる可能性があります。
5.バー開業に必要な資格
バーを開業し、法に則って運営していくためには、特定の資格取得が義務付けられています。ここでは、営業形態や規模によって、バーの開業に必要となる2つの資格について解説します。
1)食品衛生責任者
バーを含む飲食店には、店舗ごとに必ず1名、食品衛生責任者をおくことが義務付けられています。この資格は、都道府県知事などが行う講習会または、都道府県知事などが適正と認める講習会を受講することで取得でき、食品の安全や衛生管理に関する知識を身につけられます。
2)防火責任者
店舗の収容人数が30名以上の(不特定多数の人が出入りする建物の)場合、防火管理者をおくことが消防法で義務付けられています。防火管理者は、防火に関する知識や技能を習得し、火災の予防や、災害時の避難誘導の責任を負います。
6.バー開業に必要な届け出
バーを開業する際には、事業をはじめることを関係機関に知らせるためのさまざまな届け出が必要です。以下に、バーの開業に必要な主な届け出をまとめました。
1)開業届
個人事業主としてバーをはじめる場合、事業を開始したことを税務署に知らせるための「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。開業から1ヶ月以内に提出しなければなりません。
2)飲食店営業許可
バーを営業するためには、都道府県知事の許可が必要です。店舗の構造が規定を満たしているか、食品衛生責任者がいるかなどの要件を満たしたうえで、保健所に申請をおこないます。
3)深夜酒類提供飲食店営業開始届
午前0時から6時までの間に、主にお酒を提供するバーを営業する場合に必要となる届け出です。風俗営業法の規制を受け、営業開始の10日前までに警察署に提出しなければなりません。
4)防火管理者選任届出
店舗の収容人数が30名以上の場合、防火管理者を選任したことを消防署に届け出る必要があります。
5)特定遊興飲食店営業許可申請
バーの一部で、客にダンスをさせたり、カラオケなど遊興的なサービスを提供したりする場合に必要となる許可です。申請手続きが複雑であるため、許可が必要となるか否かの判断を含めて専門家へ相談することが推奨されます。
7.はじめての創業融資はドリームゲートの事業計画書作成サポートツール
バー開業は、資金調達から各種手続きまで、多くの準備が必要となります。とくに創業融資は、事業の成否を左右する重要なプロセスです。金融機関からの信用を得るためには、説得力のある事業計画書を作成することが何よりも重要となります。
「ドリームゲート」では、事業計画書の作成を支援するために「事業計画書作成サポートツール」を提供しています。このツールを活用すれば、はじめての方でも専門的な知見に基づいた事業計画書を効率的に作成できます。バー開業という夢の実現に向けて、ぜひ一度利用してみてはいかがでしょうか。
- 累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる
- 12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定

元日本政策金融公庫の融資課長として5000名以上の起業家を支援した上野アドバイザー。現在は、資金調達の専門家として活躍されております。融資を検討されている方はぜひご相談ください。
著書「事業計画書は1枚にまとめなさい」「起業は1冊のノートから始めなさい」など。
プロフィールを見る>>