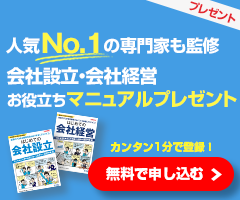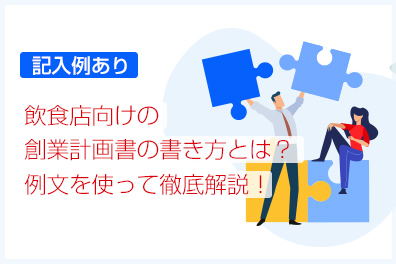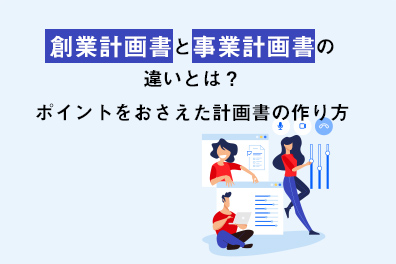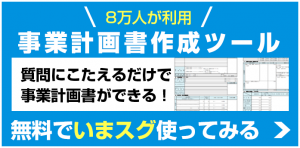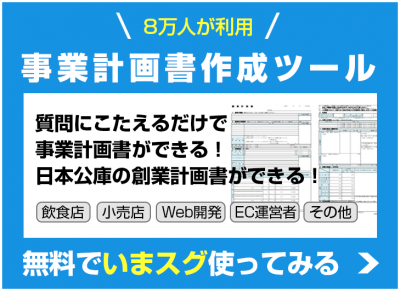「事業計画書って誰に頼むべき?」そんな疑問に融資のプロが答えます
起業や事業拡大において、資金調達は避けて通れない重要なプロセスです。その際に必要となる事業計画書は、金融機関からの融資を成功させるための羅針盤といえるでしょう。「事業計画書を作成したいけれど、誰に相談するのが最適なのか分からない」とお悩みの方も少なくないはずです。
本記事では、融資の現場を熟知する専門家の視点から、事業計画書を誰に頼むべきか、それぞれの専門家の特徴や費用相場、依頼する際の注意点などをくわしく解説します。事業計画書の作成でお困りの起業家や経営者にとって、最適なパートナー選びの一助となれば幸いです。
8万人が利用した事業計画書作成ツール
ブラウザ上の操作で事業計画を作成、創業計画書もエクセルでダウンロード可能
元日本政策金融公庫の融資課長として5000名以上の起業家を支援した上野アドバイザー。現在は、資金調達の専門家として活躍されております。融資を検討されている方はぜひご相談ください。
著書「事業計画書は1枚にまとめなさい」「起業は1冊のノートから始めなさい」など。
プロフィールを見る>>
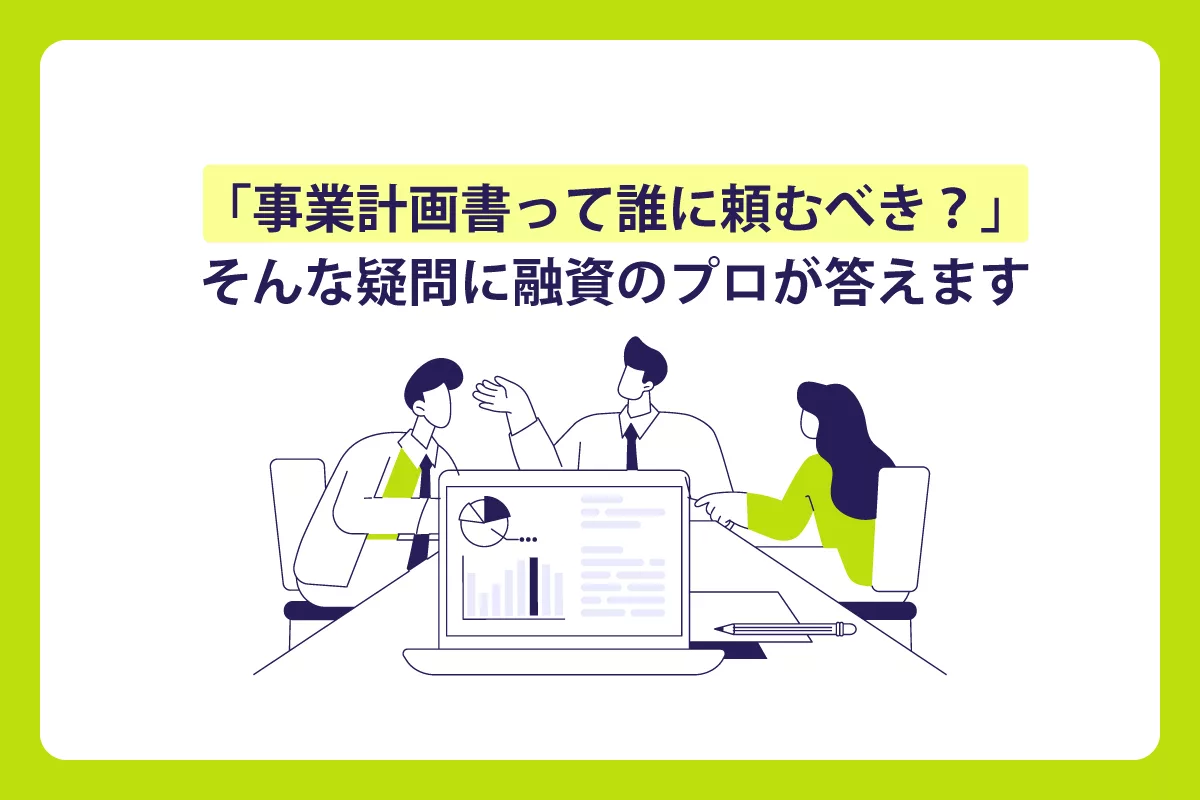
目次
1.そもそも事業計画書とは
事業計画書とは、事業の目的や目標、それを達成するための具体的な戦略、収益の見込みなどをまとめた計画書です。事業計画書は、金融機関からの融資審査において、企業の将来性や返済能力を確認するための重要な判断材料となります。
また、単に融資を受けるためだけでなく、経営者自身が事業の全体像を把握し、具体的な行動計画に落としこむためのツールとしても活用できます。この計画書には、事業のコンセプト・市場分析・競合分析・マーケティング戦略・組織体制、そして財務計画など、多岐にわたる要素を盛りこむ必要があります。
詳細かつ実現可能性の高い事業計画書を作成することは、事業の成功に向けた第一歩といえるでしょう。
参考:事業計画書の実例が無料で見れる!実例から事業計画書の書き方を習得しよう
2.事業計画書は誰に頼めるか
事業計画書の作成を依頼できる専門家は多岐にわたり、それぞれ専門知識や得意分野が異なります。税理士・公認会計士・弁護士・中小企業診断士といった士業のほか、民間のコンサルタント、さらには商工会議所・商工会、よろず支援拠点なども選択肢として挙げられます。
参考:起業の相談 誰にする?
1)税理士
税理士は、税務に関する専門家であり、日々の会計処理や決算書の作成、税務申告などを主な業務としています。企業の財務状況を正確に把握できるため、事業計画書の財務計画部分の作成を依頼する際に強みを発揮します。
過去の財務データに基づいた予測や、節税対策を踏まえた資金計画などを立案してもらえる可能性があります。ただし、税理士によっては融資に関する知識や経験が豊富でない場合もあるため、事前に確認することが重要です。
2)公認会計士
公認会計士は、会計監査を主な業務とする会計の専門家です。財務諸表の信頼性を保証する立場から、企業の財務状況を厳しく分析する能力に長けています。事業計画書の財務計画においても、より厳密な視点からのチェックやアドバイスが期待できます。
大規模な資金調達や、株式公開(IPO)を目指すような場合には、公認会計士の専門知識が役立つでしょう。
3)弁護士
弁護士は、法律の専門家であり、契約書の作成や法律相談などを主な業務としています。事業計画書においては、法的な側面からのアドバイスや、事業展開におけるリスク分析などを依頼できます。新規事業で法規制が関わる場合や、契約関係が複雑になるような場合には、弁護士の視点が重要となるでしょう。
4)中小企業診断士
中小企業診断士は、中小企業の経営課題に対して専門的な診断や助言をおこなう専門家です。経営戦略・マーケティング・財務など、幅広い知識を有しており、事業全体の視点から事業計画書の作成をサポートしてくれます。融資はもちろん、事業の成長戦略についても相談したい場合に適しています。
5)民間コンサルタント
民間のコンサルタントは、特定の業界や分野に特化した専門知識やノウハウを持っている場合があります。融資支援に特化したコンサルタントも存在し、金融機関との交渉術や、審査のポイントなどを熟知している可能性があります。自社の事業内容や成長戦略に合致したコンサルタントを選ぶことが重要です。
6)商工会議所・商工会
商工会議所や商工会は、地域の中小企業を支援する団体です。主に会員企業に対して、経営相談や融資に関するアドバイスをおこなっています。一定期間以上所属することで、日本政策金融公庫の担当者を紹介してくれる場合があり、「マル経融資」を受けられる可能性があります。
マル経融資は、無担保・無保証人で利用できる小規模事業者向けの低利率の融資制度です。商工会議所や商工会が日本政策金融公庫へ推薦して、日本政策金融公庫が融資をする制度です。
したがって、マルケイ融資を利用したい場合は、商工会議所・商工会への加入を検討するのが賢明な選択といえるでしょう。会員企業でなくとも経営相談などは可能ですが、まずは年会費を支払い加入することをおすすめします。
7)日本政策金融公庫の相談窓口
日本政策金融公庫は、中小企業や創業間もない企業を支援する政府系金融機関です。融資に関する相談窓口を設けており、事業計画書の作成に関するアドバイスや、融資制度の説明を受けることができます。
無料で相談できるため、まずは相談してみるのもよいでしょう。ただし、あくまでアドバイスであり、事業計画書の作成代行はおこなっていません。
- 累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる
- 12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定
3.事業計画書の制作代行の費用・相場
事業計画書の作成代行を専門家に依頼する場合、費用は依頼する専門家や、事業計画書の複雑さ、ボリュームなどによって大きく異なります。主な料金体系としては、固定報酬型、成功報酬型、そして両者を組み合わせたパターンがあります。
1)固定報酬
固定報酬型は、事業計画書の作成にかかる費用を事前に確定する方式です。一般的には、10万円から15万円程度が相場とされていますが、事業の規模や複雑さによってはさらに高額になることもあります。
この方式のメリットは、費用が事前に確定するため、予算管理がしやすい点です。しかし、融資が成立しなかった場合でも費用が発生するというデメリットがあります。
2)成功報酬型
成功報酬型は、融資がじっさいに成立した場合にのみ報酬が発生する方式です。報酬額は、融資金額の一定割合で定められることが多く、融資金額が大きくなるほど報酬額も高くなります。
出資法により、融資金額に対する成功報酬の上限は5%以内と定められており、金額が上がるにつれてパーセンテージが下がる傾向にあります。また、コンサルタントによっては、報酬額の交渉に応じる場合もあります。
この方式のメリットは、融資が成立しなければ費用が発生しないため、初期費用を抑えられる点です。融資金額によっては高額な報酬となる可能性もあります。
3)固定報酬と成功報酬を組み合わせたパターンも
固定報酬と成功報酬を組み合わせた料金体系もあります。たとえば、着手金として一定額を支払い、融資が成立した場合に追加で成功報酬を支払うといった形式です。この方式は、固定報酬型と成功報酬型のそれぞれのメリットとデメリットを考慮したものであり、両者の中間的な位置づけといえるでしょう。
4.事業計画書の作成代行のメリット
事業計画書の作成代行を依頼する主なメリットは、時間と労力を大幅に削減できること、そして融資のプロの視点を取り入れることで成功確率を高められる可能性があることです。
1)大幅に時間を削減し、事業そのものに集中できる
事業計画書の作成には、多くの時間と労力が必要です。市場調査・競合分析・財務予測など、専門的な知識やスキルが求められる作業も少なくありません。これらの作業を専門家に依頼することで、経営者は本来の事業活動に集中できます。
とくに起業初期や事業拡大期においては、時間こそがもっとも貴重な資源といえるため、専門家の力を借りることで効率的に事業を進めることができるでしょう。
2)融資のプロに依頼できれば成功確率が上がる
融資の専門家は、金融機関の審査基準や融資のポイントを熟知しています。彼らに事業計画書の作成を依頼することで、金融機関が重視する要素を盛り込んだ説得力のある事業計画書を作成できます。
また、金融機関との交渉を代行してくれる場合もあり、融資の成功確率を高めることが期待できます。
5.事業計画書の作成代行を依頼する際の注意点
事業計画書の作成代行を依頼する際には、いくつかの重要な注意点があります。
事業計画書の内容以上に決算書が重要であることや、税理士が必ずしも融資に精通しているわけではないことには注意が必要です。コンサルタントに丸投げした事業計画書は金融機関に敬遠される傾向があることなども理解しておく必要があります。また、経営者自身が数字に強くなることの重要性も忘れてはなりません。
1)事業計画書より決算書の方が圧倒的に重要
金融機関が融資審査においてもっとも重視するのは、過去の財務状況を示す決算書です。客観的な実績に基づいて企業の返済能力を判断するため、将来の計画である事業計画書よりも、過去の数字が重要視されるのは当然といえるでしょう。どんなに素晴らしい事業計画書を作成しても、過去の業績がともなっていなければ融資を受けることは難しいのが現実です。
したがって事業計画書だけに多額のコストをかけるのではなく、日々の業務をしっかりとおこない、業績を積み上げることこそが、融資成功への近道であると心得ましょう。客観性のない計画では、融資担当者を納得させることはできません。
2)多くの税理士は銀行融資に精通していない
税理士は税務の専門家であり、主な業務は納税に関するアドバイスや手続きの代行で、必ずしも銀行融資に精通しているとは限りません。融資に関する知識や経験が不足している税理士に依頼しても、金融機関の審査ポイントを押さえた事業計画書の作成は困難です。
税理士を選ぶ際には、融資支援の実績やノウハウがあるかどうかを確認することが重要です。税理士の仕事は、あくまでも税務相談である点を忘れないようにしましょう。
3)コンサルに丸投げした事業計画書を銀行員は嫌がる
最近では、銀行融資の際に税理士やコンサルタントの同席を認めないケースが増えています。金融機関は、経営者自身が事業内容や計画をしっかりと理解し、自分の言葉で説明できるかどうかを重視しています。
コンサルタントに丸投げで作成してもらった事業計画書では、内容を十分に理解できていないと判断され、融資審査に悪影響を及ぼす可能性があります。代行してもらった場合でも、必ず内容を精読し、自分の言葉で説明できるように準備しておく必要があります。経営者が自分で事業計画書を作成しているかを銀行員は重視しているのです。
4)数字に弱い経営者は長期的に成功することはできない
「事業を興すのは得意だが数字は苦手だ」という経営者は少なくありません。しかし、資金調達は、ある意味で経営者のもっとも重要な仕事のひとつです。事業を成長させていくためには、財務状況を常に把握し、適切な資金調達をおこなう必要があります。
事業計画書の作成を通じて、ある程度自分で数字を理解し、計画を立てられるようになることが、長期的な事業の成功に繋がります。そのため、事業計画書は自分で作成できるようになることがベストです。
6.自分で事業計画書を作成する方法
事業計画書は、可能な限り自分の手で作成することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けながら、自社の事業を深く理解し、将来像を描くことで、より実現可能性の高い計画を策定できます。
専門家に相談し銀行融資に対する知見を深め、そのうえで自分の手で時間をかけて作成するのが理想です。
1)客観的に自社や市場環境を分析する
まずは、自社の強みや弱み、競合の状況、市場の動向などを客観的に分析することが重要です。データや根拠に基づいた分析をおこなうことで、実現可能性の高い事業計画を作成できます。
2)整合性が取れるように意識する
事業計画書の各項目(事業内容・マーケティング戦略・財務計画など)が相互に矛盾しないように、整合性を意識して作成する必要があります。たとえば、売上目標と販促計画、人員計画などが整合しているかを確認しましょう。
3)ツールを活用する
事業計画書の作成を効率化し、質の向上を図るうえで、ツールの活用は非常に有効な手段となります。とくに事業計画書作成に特化したツールは、必要な項目が体系的に整理されており、入力の手順に沿って進めるだけで、網羅的かつ論理的な事業計画書を作成することが可能です。市場分析や財務予測などのテンプレートが用意されている場合もあり、専門知識が不足している場合でも安心して利用できます。
数多くのツールが存在するなかでも、とくにおすすめなのがドリームゲートの事業計画書作成サポートツールです。かんたんな質問に答えるだけで、本格的な事業計画書をスムーズに作成できる点が大きな特徴です。
Excel形式での出力も可能であるため、作成後の修正や調整も容易におこなえます。事業計画書の作成に不安を感じている方は、ぜひ一度ドリームゲートの事業計画書作成サポートツールルを試してみてはいかがでしょうか。
7.自分で作成するなら「ドリームゲート」の事業計画書作成サポートツール!
事業計画書の作成に不安を感じている方も、ドリームゲートの事業計画書作成サポートツールを使えば、かんたんな質問に答えるだけで、本格的な事業計画書を自分で作成できます。
このツールは事業の基本情報から、市場分析・競合分析・マーケティング戦略、そして収支計画書まで、事業計画書に必要な要素を網羅的にカバーしています。質問に沿って入力していくだけで、論理的で分かりやすい事業計画書が完成します。
さらに、作成した事業計画書はExcel形式でダウンロードできるため、必要に応じて自由に修正や加筆をおこなうことができます。金融機関への提出はもちろん、社内での検討資料としても活用可能です。
専門家に依頼する前に、まずドリームゲートの事業計画書作成サポートツールを試してみてはいかがでしょうか。自分で事業計画を作成する過程で、事業に対する理解が深まり、自信を持って資金調達に臨むことができるはずです。
- 累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる
- 12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定

元日本政策金融公庫の融資課長として5000名以上の起業家を支援した上野アドバイザー。現在は、資金調達の専門家として活躍されております。融資を検討されている方はぜひご相談ください。
著書「事業計画書は1枚にまとめなさい」「起業は1冊のノートから始めなさい」など。
プロフィールを見る>>