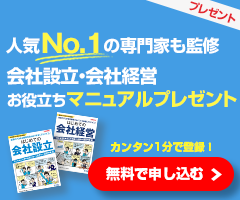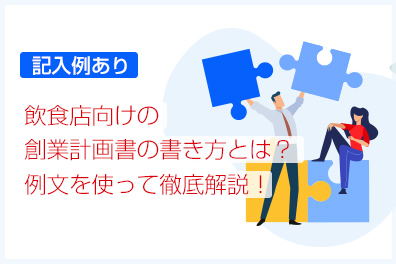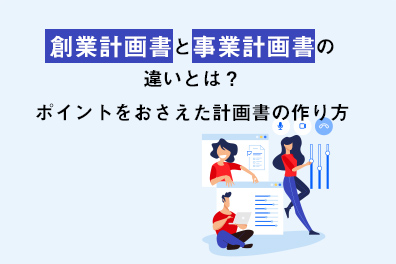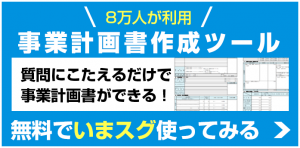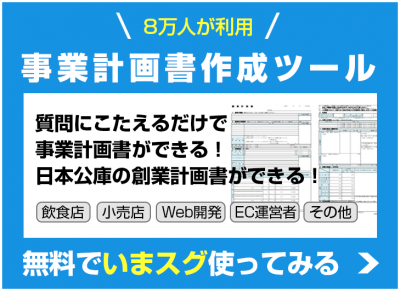公庫の創業融資は何年まで受けられる? そんな疑問に元・公庫融資課長が回答!
創業を志す多くの起業家にとって、資金調達は事業を軌道に乗せるうえで避けて通れない課題のひとつです。とくに、日本政策金融公庫の提供する創業融資は、その手厚いサポートと利用しやすさから、多くの起業家にとって魅力的な選択肢となっています。しかし、「創業融資は創業後何年まで利用できるのか?」という疑問を抱く方も少なくありません。
そこで本記事では、長年起業支援に携わってきたプロの視点から、公庫の創業融資制度の詳細を深掘りし、その利用条件や成功のポイントについて解説いたします。本記事が起業の夢を実現させるための一助となれば幸いです。
8万人が利用した事業計画書作成ツール
ブラウザ上の操作で事業計画を作成、創業計画書もエクセルでダウンロード可能
元日本政策金融公庫の融資課長として5000名以上の起業家を支援した上野アドバイザー。現在は、資金調達の専門家として活躍されております。融資を検討されている方はぜひご相談ください。
著書「事業計画書は1枚にまとめなさい」「起業は1冊のノートから始めなさい」など。
プロフィールを見る>>
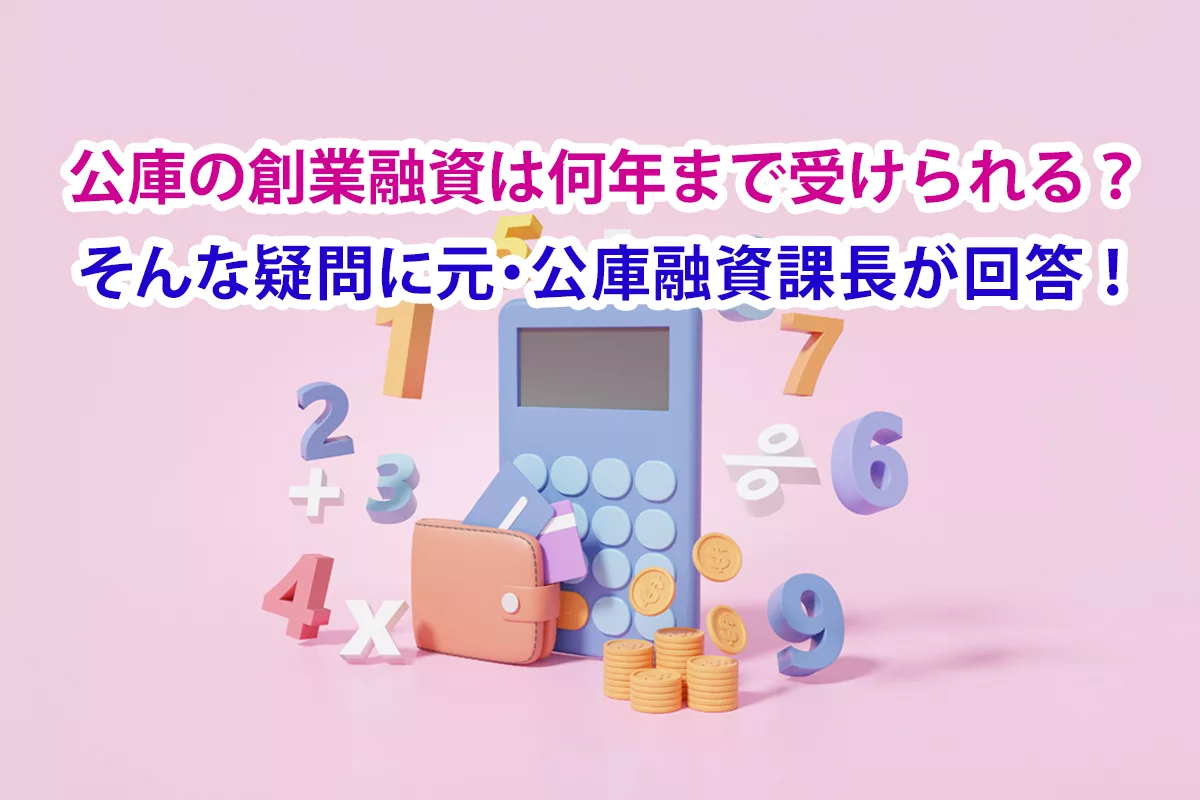
目次
1.そもそも創業融資とは?
創業融資とは、新たに事業をはじめる方や、事業を開始して間もない方が、事業の立ち上げや運転に必要な資金を調達するために利用できる融資制度の総称です。一般的な融資と比較して、事業実績がない段階でも利用しやすいように、さまざまな優遇措置が設けられているのが特徴です。
とくに、日本政策金融公庫が提供する創業融資は、その充実した内容から多くの起業家に選ばれています。創業融資制度は、事業の初期段階における資金繰りの不安を軽減し、起業家が事業に専念できる環境を整えることを目的としています。
2.公庫の創業融資制度のポイント
公庫が提供する創業融資制度は、「新規開業・スタートアップ支援資金」が主な制度ですが、業種によっては「生活衛生新企業育成資金」という制度に該当することもあります。ここでは、公庫の創業融資のポイントを解説します。
1)新規開業・スタートアップ支援資金
「新規開業・スタートアップ支援資金」は、新たに事業を始める方、または事業を開始してからおおむね7年以内の方を対象とした融資制度です。この制度は、創業期の企業が直面するさまざまな資金ニーズに対応できるよう設計されており、設備資金や運転資金として幅広く利用できる柔軟性が魅力です。事業の立ち上げ期において、安定した経営基盤を構築するための重要な資金源となりえるでしょう。
創業者の状況によっては、基準利率よりも低い特別利率が適用されます。
たとえば、「女性の方、35歳未満または55歳以上の方」「創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて新たに事業を始める方」などが該当します。
さらに「新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方」の場合は、「創業支援貸付利率特例制度」という利率低減の制度を利用できます。
2)生活衛生新企業育成資金
美容業、飲食業、旅館業など「生活衛生関係営業」の場合は、原則として「生活衛生新企業育成資金」の対象となります。この制度は、振興計画認定組合の組合員向けの「振興事業貸付」とそれ以外の方向けの「一般貸付」があります。
「生活衛生新企業育成資金」の特徴は、融資限度額が設備資金で7億2,000万円(振興計画認定組合員向けの場合)と高額である点です。ホテルや旅館など、高額の融資を必要とする業種を想定しているためです。ただし、数千万円以上など高額融資の場合は、不動産等の担保の提供を求められることがほとんどです。
「新規開業・スタートアップ支援資金」と同様に、創業者の状況によっては「創業支援貸付利率特例制度」など、低利率の融資が適用されます。
※「生活衛生関係営業」の方でも、「新規開業・スタートアップ支援資金」が利用できるケースもあります(女性の方、35歳未満または55歳以上の方の場合など)。
- 累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる
- 12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定
3.公庫の創業融資に関して知っておくべきこと
創業融資を受けるためには、制度のしくみだけでなく、申請のタイミングや利用できるほかの制度、そして民間金融機関との関係性についても理解を深めておくことが重要となります。
1)融資担当者が適した制度を教えてくれる
公庫の創業融資のポイントについて解説しましたが、多くの方が「自分は融資制度や利率など、どれに該当するのか分からない」と感じるものです。
しかし、心配する必要はありません。公庫の担当者が、提出された事業計画書や面談を通じて、申請者の事業状況や資金使途などを総合的に判断し、もっとも適した有利な制度を適用してくれます。
2)創業融資は事業開始前に申請すべし
創業融資は、事業開始前からでも申請が可能です。むしろ、事業開始前に申請する方が、融資を受けられる可能性が高まる傾向にあります。事業開始前であれば、過去の実績にとらわれず、将来の事業計画や起業家の熱意、能力が重視されるためです。
一方、事業開始後になると、じっさいの売上や利益といった実績が審査の対象となり、計画どおりに進んでいない場合は不利になることも考えられます。遅くとも事業開始後2〜3ヶ月以内には申請を済ませておくことが望ましいでしょう。
3)経営者保証免除特例制度を利用すべし
公庫の創業融資における最大の魅力のひとつに「経営者保証免除特例制度」を利用できる点があります。これは、株式会社など法人で融資を受ける際に、経営者の個人保証が不要になる制度です。この制度を利用できれば、融資実行時に経営者個人の連帯保証が不要となり、万一事業がうまくいかなかった場合でも、個人の資産が守られる可能性が高まります。
創業融資の場合「新たに事業を始める方または税務申告を2期終えていない方」が対象になります。ただし「経営者保証免除特例制度」の場合は利率の上乗せがあるので、「選択せず個人保証をする」という選択も可能です。
ここで対象者に関して、一つ留意点があります。すでに個人事業で開業し、その個人事業を法人化した場合は、個人事業における税務申告もカウントされます。たとえば、個人事業で税務申告を2期終えてから法人成りした場合は非対象となります。
4)保証協会付き融資も検討すべし
公庫以外の創業融資を検討するのであれば、信用保証協会付き融資も視野に入れましょう。事業実績がないなかで、いきなりプロパー融資(信用保証協会の保証を利用しない金融機関からの直接融資)を受けることは非常に難しいのが現状です。
信用保証協会付き融資は、信用保証協会が債務保証をおこなうことで、金融機関による融資を容易にする制度です。また、地方自治体が提供する制度融資も、実質的には信用保証協会付き融資と同じしくみであることがほとんどです。
政府系金融機関である公庫は、民間金融機関との協調融資にも積極的です。たとえば創業に高額の資金が必要な場合などは、公庫と民間金融機関を並行して利用することで希望額の融資を受けられる可能性があります。信用保証協会付きの創業融資は、創業後5年未満を対象としているケースが多く、公庫と並行して検討する価値は十分にあります。
参考:創業融資における信用保証協会の役割とは?|資金調達のプロが公庫と徹底比較
- 累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる
- 12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定
4.公庫の創業融資に必要な書類
公庫の創業融資を成功させるためには、必要な書類を漏れなく、かつ説得力のある内容で準備することが非常に重要です。提出書類は多岐にわたりますが、融資初心者がとくに意識すべき主要な書類を解説します。これらの書類は、審査においてあなたの事業の実現可能性を伝えるための重要なツールとなります。
1)創業計画書
創業融資において、創業計画書はもっとも重要な書類といっても過言ではありません。なぜなら、事業の実績がない段階では、創業計画書こそがあなたの事業の将来性、実現可能性、そしてあなたの熱意や能力を判断する唯一の手がかりとなるからです。
創業計画書の作成に際しては、単に項目を埋めるだけでなく、市場分析、競合との差別化、具体的な事業戦略、収益の見込み、資金使途などを具体的に記述することが必要です。客観的なデータや根拠に基づいた説得力のある内容に仕上げることも求められます。とくに、事業の強みや独自性を明確にアピールする構成を意識しましょう。
2)自己資金
公庫の創業融資において、明確な自己資金の割合は定められていません。しかし、一般的に創業に必要な金額の3割程度が、自己資金の目安とされています。自己資金は、起業家の事業に対する本気度を示す指標として重要視されます。
また、自己資金が多いほど、融資後の返済負担が軽減され、事業の継続性が高まると判断される傾向にあります。預貯金だけでなく、親族からの贈与や退職金なども自己資金として認められる場合がありますが、その出所を明確に説明できるよう準備しておく必要があります。
3)月別収支計画書(資金繰り計画書)
絶対条件ではありませんが、月別収支計画書を提出することで融資審査における印象を格段に向上させることができます。融資は一度受けて終わりではなく、その後の事業の継続的な発展を見据えたものでなければなりません。
そのため、融資後の資金繰りが見通せる計画書は、返済能力と事業の安定性をアピールするうえで非常に有効です。できれば今後5年程度の資金繰り表を作成し、売上や経費の具体的な根拠、季節変動などを考慮した現実的な計画を提示することが望ましいでしょう。
4)見積書
資金使途が設備資金の場合、購入予定の設備に関する見積書の提出は必須です。見積書は、融資資金が適切に、かつ計画どおりに設備投資に充てられることを証明するために必要となります。
創業融資に限らず、融資の際には資金使途を明確にし、その資金が何に使われるのか、それが事業にどのように貢献するのかを具体的に説明することが求められます。また、融資実行後は、説明された使途のとおりに資金が使用されたことを証明する書類(領収書など)の提出が必要となります。正確な見積書を準備し、資金の管理を徹底することが重要です。
5)各種ローンの支払明細
もし住宅ローンや自動車ローンなど、ほかに借入れがある場合は、必ず支払明細などを提出する必要があります。創業融資に限らず、融資を受ける際には、ほかの借入れに関する情報をすべて開示することが求められます。これは、あなたの返済能力を総合的に判断するためです。
隠蔽や虚偽の申告は、融資の審査に悪影響を及ぼし、最悪の場合、融資が受けられなくなる可能性もあります。すべての情報を正直に開示し、返済計画に無理がないことを説明できるよう準備しましょう。
5.創業融資の成功率アップにはドリームゲートの事業計画書作成サポートツール
創業融資の成功において、もっとも重要な要素のひとつが、説得力のある事業計画書の作成です。とくにはじめて融資を申込む方にとって、ゼロから完璧な事業計画書を作成することは容易ではありません。
そこで活用したいのが、ドリームゲートが提供する事業計画書作成サポートツールです。このツールは、創業計画書の作成に必要な項目を網羅しており、ステップバイステップの入力で、高品質な事業計画書を効率的に作成できるよう設計されています。
テンプレートの活用や具体的な記入例が豊富に用意されているため、事業のアイデアを具体的な計画に落としこむ作業を強力に支援してくれます。ツールの活用は、事業の魅力を最大化し、融資成功の確率を大幅に高めることに繋がるでしょう。

元日本政策金融公庫の融資課長として5000名以上の起業家を支援した上野アドバイザー。現在は、資金調達の専門家として活躍されております。融資を検討されている方はぜひご相談ください。
著書「事業計画書は1枚にまとめなさい」「起業は1冊のノートから始めなさい」など。
プロフィールを見る>>