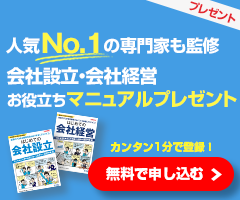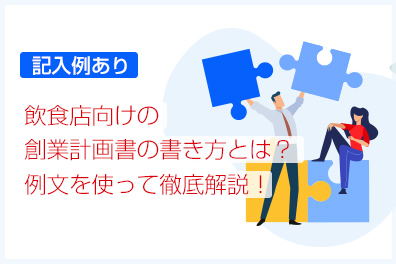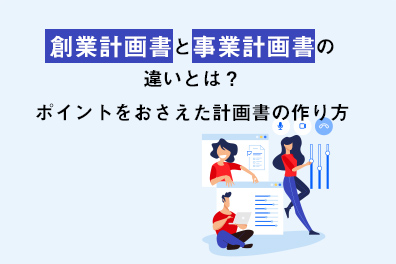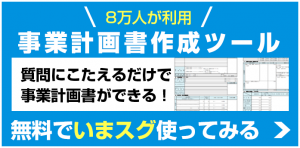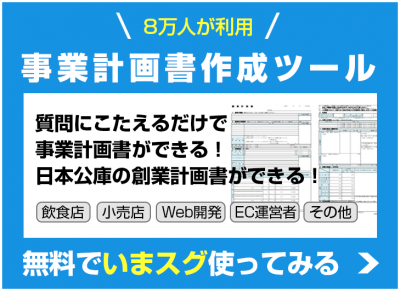【はじめての資金調達】誰でもわかるイロハを融資のプロが大公開
起業を志す多くの皆様にとって、事業の成功を左右する重要な要素のひとつが資金調達です。アイデアや情熱だけでは事業を継続することは困難であり、いかにして必要な資金を確保するかは、起業の第一歩として極めて重要な課題といえるでしょう。しかし、はじめての資金調達は、その複雑な制度や専門的知識の必要性から、多くの起業家を悩ませる要因でもあります。
そこで本記事では、皆様が安心して起業に臨めるよう、資金調達の基本的な考え方から具体的な方法そして成功に導くためのポイントまで、融資のプロの視点からわかりやすく解説します。
8万人が利用した事業計画書作成ツール
ブラウザ上の操作で事業計画を作成、創業計画書もエクセルでダウンロード可能
元日本政策金融公庫の融資課長として5000名以上の起業家を支援した上野アドバイザー。現在は、資金調達の専門家として活躍されております。融資を検討されている方はぜひご相談ください。
著書「事業計画書は1枚にまとめなさい」「起業は1冊のノートから始めなさい」など。
プロフィールを見る>>
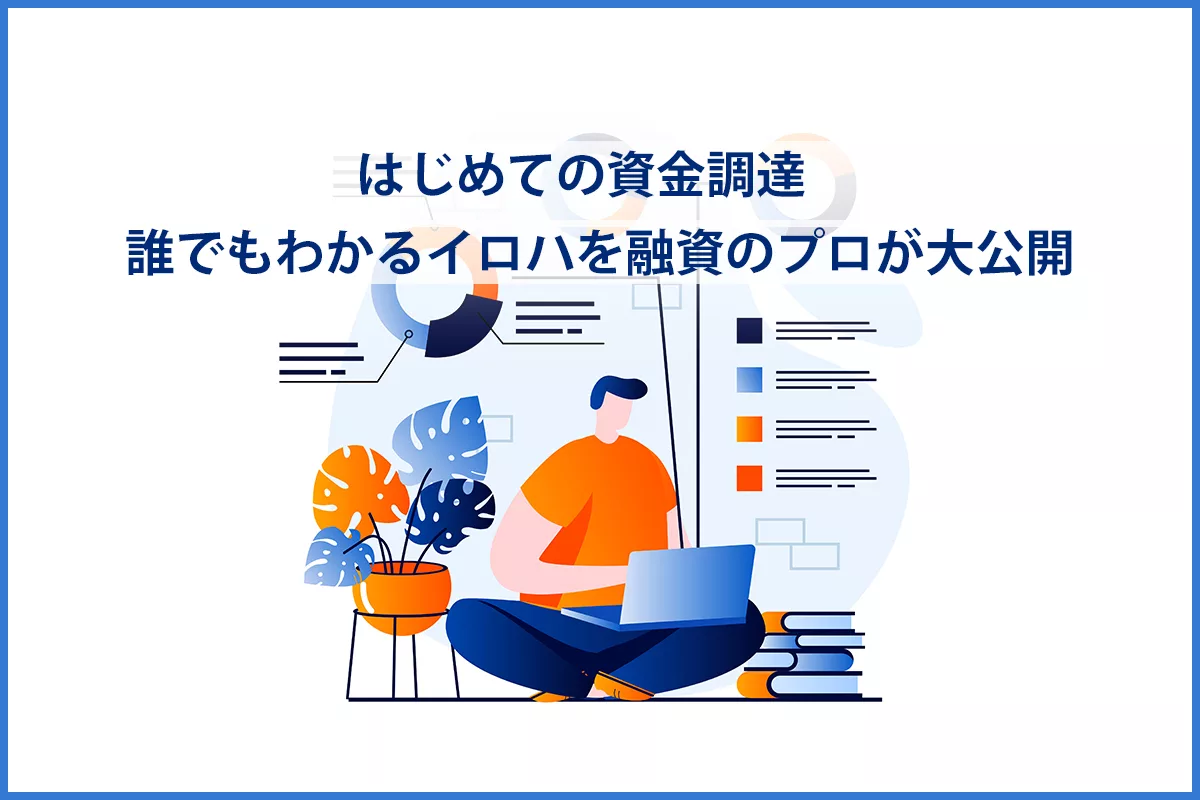
目次
1.そもそも資金調達とは
資金調達とは事業をはじめる、あるいは継続していくうえで必要となる資金を外部から調達することです。資金調達は、自己資金だけでは賄いきれない事業運営費や設備投資費などを補うために不可欠な行為といえるでしょう。
資金は大きく分けて、日々の事業活動に必要な運転資金と、事業拡大や新たな設備導入などに使われる設備資金の2種類に分類されます。運転資金は「仕入れ費用、人件費、家賃、広告宣伝費」など、継続的に発生する事業用の経費を指し、事業の円滑な運営に直結します。
一方、設備資金は「事務所の建設、機械装置の購入、車両の導入」など、事業の基盤を形成したり生産性を向上させたりするための投資に使われる資金であり、長期的な視点での事業成長を支えるものです。
2.創業時の資金調達方法は大きく分けて4つ
創業期における資金調達は、事業のスタートダッシュを決めるうえで非常に重要であり、多様な選択肢のなかから自社に最適な方法を見極める必要があります。どのような手段を選択するにせよ、基本的に自己資金が多いほど金融機関や投資家からの信頼を得やすく、調達の可能性を高めることにつながるでしょう。
参考:「自己資金は3割必要」ってホント!? 元・銀行支店長が教える、創業融資の必勝法②資金計画
1)融資(デットファイナンス)
はじめての資金調達において、比較的多くの起業家が選択肢として検討するのが融資、すなわちデットファイナンスです。これは、金融機関などから資金を借入れ、将来的に返済していく方法を指します。とくに創業期においては、以下2つの機関からの融資が主要な選択肢となるでしょう。
日本政策金融公庫は政府系金融機関であり、中小企業や小規模事業者そして創業を考えている方々に対して、有利な条件で融資を提供していることで知られています。創業間もない企業でも実績を問われにくい「新規開業・スタートアップ支援資金」など、独自の融資制度が充実しており、はじめての資金調達では有力な候補のひとつとなるはずです。
次に挙げられるのが、信用保証協会の保証付き融資です。これは、銀行などの金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会が融資の保証人となることで、企業が融資を受けやすくする制度を指します。信用保証協会が保証することで、金融機関は貸し倒れのリスクを軽減できるため、実績が少ない創業企業でも融資を受けられる可能性が高まるでしょう。ただし、保証料が必要となる点には留意が必要です。
一方で、手軽に利用できるビジネスローンも存在しますが、これは利息が高い傾向にあります。緊急時に限り利用する最終手段として位置づけ、安易な利用は避けるべきでしょう。事業計画に基づいた堅実な資金調達計画が不可欠となります。
2)出資(エクイティファイナンス)
融資とは異なり、株式を発行して投資家から資金を調達する方法が出資、またはエクイティファイナンスです。この場合、返済義務は発生せず、投資家は企業の成長による株価上昇や配当を期待して資金を提供します。創業期の出資では、主に以下の2つのタイプが一般的です。
ベンチャーキャピタル(VC)は、将来性の高い未上場企業に対し、成長資金として出資をおこなう投資会社です。彼らは単に資金を提供するだけでなく、経営戦略やネットワークの提供など、多角的な支援を通じて企業の成長を後押しすることが多く、とくに革新的な技術やサービスを持つスタートアップ企業にとって魅力的な選択肢となるでしょう。
VCは、将来的な株式公開(IPO)やM&Aによるリターンを目的としているため、事業の成長性が重視されます。
もうひとつの選択肢は、エンジェル投資家(個人投資家)からの出資です。エンジェル投資家は、個人の資産を投じて、将来性のある創業間もない企業を支援する投資家を指します。
彼らのなかには、自身の経験や専門知識を活かして経営のアドバイスをおこなう者も多く、資金面だけでなく、メンターとしての役割も期待できる場合があります。エンジェル投資家はVCと比較して小規模な出資が多い傾向にありますが、柔軟な条件で資金を提供してくれることも特徴のひとつです。
参考:スタートアップの資金調達のすべて−資金調達を成功させる方法−
3)補助金・助成金
国や地方公共団体、あるいは民間団体が、特定の目的や政策達成のために支給する資金が補助金や助成金です。これらは基本的に返済義務がない点が最大の特徴であり、起業家にとって非常に魅力的な資金源となるでしょう。
たとえば「創業支援、事業の多角化、雇用促進、研究開発」など、多岐にわたる分野で公募されており、自社の事業内容と合致するものを積極的に探すことが重要です。
ただし、申請には多くの書類準備が必要であり、審査に通るためには明確な事業計画や申請条件の厳格な遵守が求められます。また、受給までにある程度の時間を要する点も考慮に入れるべきでしょう。
参考:2025年度の補助金はどうなる?~経産省の概算要求をチェック!
4)そのほか
上記以外にも、創業期に利用できる資金調達の方法はいくつか存在します。
クラウドファンディングは、インターネットを通じて不特定多数の人々から少額ずつ資金を調達するしくみです。支援者へのリターンは、製品やサービス、あるいは株式など、プロジェクトによって多岐にわたります。とくに、新しい製品やサービスを開発する際、市場のニーズを確認しながら資金を調達できるというメリットがあるでしょう。
また、各種団体や企業が主催するビジネスコンテストも、資金調達のひとつの方法となり得ます。優秀なビジネスプランには賞金が授与されるだけでなく、投資家やメンターとの出会いの場にもなり、その後の資金調達や事業拡大につながる可能性を秘めています。
さらに、社会貢献性の高い事業やNPO法人などでは、寄付による資金調達も考えられます。これは、特定の理念や活動に共感する個人や団体から、無償で資金提供を受ける方法であり、事業の公共性や社会的な意義が重視されることになります。
- 累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる
- 12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定
3.それぞれの資金調達方法のメリット・デメリット
資金調達の方法は多岐にわたり、それぞれに特有のメリットとデメリットが存在します。自社の事業モデルや成長段階、そして将来のビジョンに合致した最適な選択をするためには、これらの特性を深く理解することが不可欠です。
1)融資(デットファイナンス)
安定的な売上を継続的に創出できるビジネスモデルであれば、比較的審査にとおりやすい点が融資のメリットです。返済能力が重視されるため、堅実な事業計画と実績があれば、多額の資金を調達することも不可能ではありません。
また、経営権を第三者に譲渡することなく資金を確保できるため、経営の自由度を維持しやすいという利点も大きいでしょう。計画どおりの返済をおこなうことで、企業としての信用力を高めることにもつながります。
一方で、デメリットとしては、基本的に将来性や成長潜在力はあまり考慮されない点が挙げられます。とくに運転資金の融資は、売掛金を補填するという考え方が強く、コンサルティング業やITサービス業など売掛金が1カ月程度しかない業種では、そもそも融資の対象として見られにくい場合もあるでしょう。
事業の初期段階で赤字が続くようなケースでは、返済原資が不足するリスクも考慮しなければなりません。さらに、担保や保証が求められることもあり、個人の資産をリスクにさらす可能性も出てくるかもしれません。
2)出資(エクイティファイナンス)
将来性が評価されれば、多額の資金を一気に調達できる可能性があることが出資の大きなメリットです。とくに革新的な技術やサービスを持つスタートアップ企業にとって、出資は大きな成長の機会となるでしょう。
出資における最大の利点は、調達した資金に返済義務がないことです。これにより、資金繰りのプレッシャーから解放され、より大胆な事業投資や研究開発に集中できる環境を整えられるかもしれません。投資家からの経営ノウハウやネットワークの提供も期待でき、事業成長の加速につながる可能性があります。
しかし、デメリットとして、経営権の一部を失うことが挙げられます。出資を受けるということは、株式や持分の一部を投資家に譲渡することであり、経営に関与される可能性が出てきます。
また、投資家は最終的に株式の売却(M&A)か上場(IPO)のどちらかでエグジット(投資資金の回収)を望むため、常にそれらの目標を意識した経営が求められるでしょう。とくにITなどのトレンドに左右されやすい分野では、市場の変化に対応できない場合、投資家からのプレッシャーが大きくなることも考えられます。
3)補助金・助成金
補助金や助成金のメリットは、多くの場合、返済義務がない点に尽きます。これは、事業のキャッシュフローに直接的な負担をかけずに資金を確保できるため、非常に大きな利点です。
融資や出資の審査に落ちたとしても、補助金や助成金という別のチャンスがあるため、資金調達の選択肢を広げることができるでしょう。また、補助金や助成金の採択実績は、企業の信用力を高める効果も期待できます。
一方で、デメリットも存在します。まず、申請条件が非常に厳しかったり、複雑な申請書類の準備が必要だったりすることが多くなっています。採択されるまでのプロセスが長く、事業のタイムラインと合わない可能性もあるでしょう。
補助金・助成金は、ほとんどの場合、先に自己資金か他で調達した資金で事業を行い、その後に入金される「後払い」となります。
さらに、入金後も事業進捗の報告や使途の確認など、細かい事務作業が継続的に求められることがあり、本来の事業活動に割くべきリソースを奪われる可能性も考慮しなければなりません。また、必ずしも自社の事業に最適な補助金・助成金が見つかるとは限らないという点も認識しておくべきでしょう。
4.はじめての資金調達を成功させるための考え方
はじめての資金調達を成功させるためには、戦略的なアプローチが不可欠です。とくに、現実的な事業計画を作成することが、あらゆる資金調達の前提条件となります。実現可能性の低い計画では、どのような資金調達手段を選んでも成功は望めません。
1)融資と出資のどちらがよいか慎重に検討する
資金調達の選択において、「返済義務がない」という理由だけで安易に出資を受けると、後からトラブルになる可能性が非常に高まります。出資は経営権の一部を渡すことになり、投資家との関係性によっては、経営の自由度が著しく制限されることもあるからです。そのため、自社のビジネスモデルや創業者の性格を深く考慮し、最適な資金調達方法を見極めることが極めて重要となります。
たとえば、安定的な収益が見込めるストック型のビジネスモデルであれば、融資が向いているかもしれません。一方、高い成長性が見込まれるが先行投資が多額になるSaaSビジネスのような場合は、出資が有効な選択肢となるでしょう。重要なのは、単一の選択肢に固執するのではなく、融資と出資を組み合わせることも可能であるという視点を持つことです。たとえば、初期の運転資金は融資で賄い、その後の事業拡大フェーズで出資を募るなど、段階的な資金調達も検討できます。
2)資金調達をするタイミングを考慮する
資金調達は、事業の状況や市場の動向によって、その成功確率が大きく左右されるため、タイミングが非常に重要です。とくに融資の場合、創業前か創業後3カ月以内の申請を検討することをおすすめします。
この時期はまだ実績が乏しいため、今後の事業計画に基づいて審査がおこなわれます。そのため、将来性があれば融資を受けやすい傾向にあるからです。逆に、事業を開始してある程度の時間が経過し、赤字が続いているような状況では、実績が評価の対象となり融資のハードルが上がる可能性があります。
出資の場合は、製品が市場に適合していることを示すPMF(プロダクトマーケットフィット)が確認できてからの方が、投資家からの評価を得やすくなるでしょう。PMFとは、顧客が望む製品を適切な市場に提供できている状態を指し、この段階にいたっていれば、事業の成長性と収益性への期待値が高まります。
いずれの場合も、一度資金調達をして終わりではないことを理解しておくべきです。事業の成長には継続的な資金調達が必要となります。そのため、5年〜10年の長期的な資金調達計画の策定が不可欠であると捉え、将来を見据えた計画を立てることが成功への鍵となるでしょう。資金ショートを起こす前に、余裕をもって次の資金調達に動き出すことが肝要です。
3)必要な資金調達額を決定する
「資金調達は多ければ多いほどよい」という考え方は誤りです。過剰な資金調達は、無駄なコストを発生させたり、経営の規律を緩めたりする原因となりかねません。場合によっては、「資金調達をしない」という選択肢も有効であることを忘れてはなりません。自己資金で賄える範囲であれば、それがもっともリスクの低い選択といえるでしょう。
まず、詳細な事業計画を作成し、必要な運転資金と設備資金を具体的に算出することがスタート地点となります。そのうえで、最低でも3〜6カ月分の運転資金を確保することを基本と考えるべきです。
5.創業融資の事業計画書作成はドリームゲートのサポートツールで効率的に!
創業期における資金調達を検討されている方にとって、事業計画書の作成は、その成否を左右する極めて重要なプロセスです。しかし、はじめて事業計画書を作成する際には「どのような内容を盛り込むべきか」「どのように構成すればよいか」など、多くの疑問や不安が生じるかもしれません。
ドリームゲートが提供する事業計画書作成サポートツールは、そうした起業家の皆様を強力に支援する存在となります。このツールを活用することで、事業計画書の構成要素や記載すべきポイントが明確になり、効率的かつ質の高い計画書を作成することが可能となります。
テンプレートや具体的な記入例が豊富に用意されているため、ゼロから手探りで作成するよりも、はるかに短時間で、かつ説得力のある事業計画書を完成させられます。ぜひ活用を検討してみてください。
- 累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる
- 12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定

元日本政策金融公庫の融資課長として5000名以上の起業家を支援した上野アドバイザー。現在は、資金調達の専門家として活躍されております。融資を検討されている方はぜひご相談ください。
著書「事業計画書は1枚にまとめなさい」「起業は1冊のノートから始めなさい」など。
プロフィールを見る>>