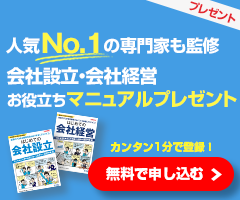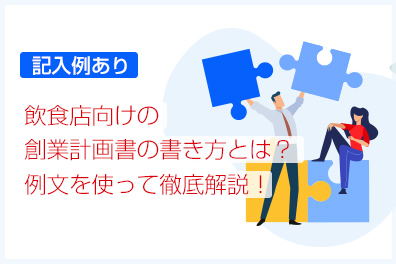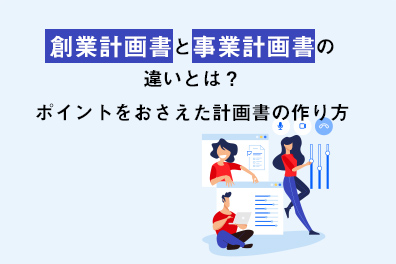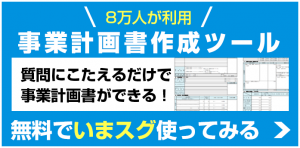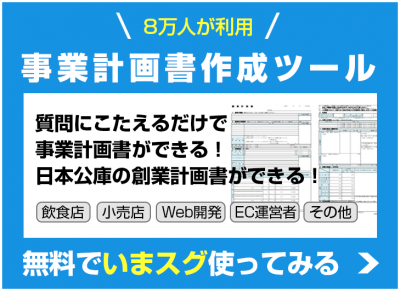銀行以外も! 起業を成功に導く開業資金の借入方法を融資のプロが解説
起業を志す皆様、開業資金の準備は順調に進んでいますか?
「夢を実現するために起業したいけど、資金が足りない…」
このようにお悩みの方も多いのではないでしょうか。開業資金の調達は、起業を成功させるための最初の難関といえるでしょう。
自己資金だけで賄うことが理想ですが、現実的には難しいケースが多いのも事実です。そこで、当記事では、融資のプロの視点から、銀行以外にも利用できる開業資金の借入方法をわかりやすく解説します。
また、もっとも一般的な借入れ先である日本政策金融公庫のおすすめポイントや、開業資金を借入れる際の注意点もくわしく説明します。当記事を最後まで読むことで、起業成功への道筋を明確化しましょう。
8万人が利用した事業計画書作成ツール
ブラウザ上の操作で事業計画を作成、創業計画書もエクセルでダウンロード可能
元日本政策金融公庫の融資課長として5000名以上の起業家を支援した上野アドバイザー。現在は、資金調達の専門家として活躍されております。融資を検討されている方はぜひご相談ください。
著書「事業計画書は1枚にまとめなさい」「起業は1冊のノートから始めなさい」など。
プロフィールを見る>>

目次
1.開業資金の借入れ方法
開業資金の借入れ先は、銀行だけではありません。政府系金融機関や信用金庫など、さまざまな選択肢があります。それぞれの特徴を理解し、自身の事業に合った借入先を選びましょう。
1)政府系金融機関
起業家にとって、もっとも利用しやすい借入れ先は、日本政策金融公庫です。政府系金融機関である日本政策金融公庫は、創業融資制度を提供しており、とくに、新規事業をはじめる方向けの「新規開業資金」は、無担保・無保証人で融資を受けられるのが大きなメリットです。
創業時は、事業の実績がないため、民間の金融機関からの融資を受けるのは難しいのが現状です。しかし、日本政策金融公庫は、政府が運営しているため、民間の金融機関よりも審査基準が緩やかで、創業間もない企業でも融資を受けやすいのが特徴です。
参考:日本政策金融公庫での創業融資の申し込みの全てを融資の専門家が徹底解説
参考:日本政策金融公庫の創業融資が大進化【元公庫融資課長が解説】
2)信用保証協会保証付融資
信用保証協会の保証付融資とは、信用保証協会が金融機関に代わって事業者の返済を保証する制度です。万が一、事業者が返済不能になった場合、信用保証協会が代位弁済するため、金融機関は安心して融資を実行できます。
信用保証協会の保証付融資は、プロパー融資よりも審査基準が緩やかです。保証料はかかりますが、この点は大きなメリットといえるでしょう。とくに、開業時の融資では、プロパー融資を受けるのは非常に難しいため、信用保証協会の保証付融資は有力な選択肢となります。
保証付融資で返済実績を残せば、将来のプロパー融資につながる可能性があるのも魅力的です。ただし、保証協会を利用するにあたって、代表者が保証人になることを求められるケースがあり、場合によっては貯金額など個人資産の記録の提出を求められることもあります。
参考:創業融資における信用保証協会の役割とは?|資金調達のプロが公庫と徹底比較
3)制度融資
制度融資とは、自治体や商工会議所などが窓口となり、金融機関と連携して融資を提供する制度です。多くの場合、信用保証協会が融資の保証をおこない、事業者の負担を軽減しています。
制度融資を利用するメリットは、金利が低く設定されている場合が多い点や、地域に密着したサポートを受けられる点です。しかし、利用条件が自治体ごとに異なるため、手続きが煩雑になる場合があります。また、地域に根ざした起業が、要件になることが多い点にも注意が必要です。
参考:都道府県の制度融資
参考:市区町村の制度融資
4)信用金庫・信用組合
信用金庫・信用組合は、地域密着型の金融機関であり、小規模事業者や地域住民に対して融資をおこなうことを目的としています。銀行と比較して規模が小さいため、個別対応に柔軟性があり、地域の実情に合わせた融資をおこなっているのが特徴です。
しかし、信用金庫・信用組合の創業融資は、地域に根ざした起業の必要があり、融資額が少額で金利もやや高めになる傾向にあります。
参考:元・信用金庫の営業マンが明かす、信用金庫の融資審査の裏側とは?
- 累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる
- 12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定
2.日本政策金融公庫の創業融資制度がおすすめな理由
数ある資金調達方法のなかでも、日本政策金融公庫の創業融資は、起業家にとってとくにメリットが多い制度です。これから事業をはじめる方にとって、心強い味方となるでしょう。ここでは、その理由を7つに分けてくわしく解説いたします。
1)無担保・無保証人で融資を受けられる
起業の初期段階では、担保となるような資産や保証人を立てることが難しい場合も多いでしょう。しかし、日本政策金融公庫の創業融資では、無担保・無保証人での融資が受けられるため、そのような心配は無用です。
一般的に、金融機関から融資を受ける際には、担保や保証人を提供する必要があります。これは、万が一、事業者が返済できなくなった場合に備え、金融機関が損失を最小限におさえるために必要な措置です。しかし、創業間もない企業にとって、担保や保証人を用意するのは容易ではありません。
その点、日本政策金融公庫の創業融資は、事業の将来性や事業計画の内容を重視するため、担保や保証人がなくても融資を受けられる可能性があります。これは、起業家にとって大きなメリットといえるでしょう。
2)低金利で融資を受けられる
政府系金融機関である日本政策金融公庫は、民間の金融機関と比較して金利が低く設定されています。金利が低ければ、利息の支払額も少なくなるため、返済の負担を軽減できます。
起業初期は、さまざまな費用がかかり、資金繰りがきびしい時期です。低金利で融資を受けられることは、事業の安定化に大きく貢献するでしょう。
3)長期返済できる
返済期間が長ければ、月々の返済額をおさえ、無理のない返済計画を立てることができます。
日本政策金融公庫の創業融資では、長期返済が可能なため、資金繰りに余裕を持たせることができます。返済期間が長ければ、月々の返済額をおさえることができるため、事業の成長に資金を再投資しやすくなるというメリットもあります。
4)実績がなくても融資を受けられる
創業間もない企業にとって、実績がないことは当然です。しかし、民間の金融機関では、実績がない企業への融資は慎重になる傾向があります。
その点、日本政策金融公庫の創業融資制度は、実績がなくても、事業計画の内容がしっかりしていれば融資を受けられる可能性があります。事業にかける熱意や将来性を評価してくれるため、起業家にとって心強い制度といえるでしょう。
5)自己資金が少なくても融資を受けられる
起業する際に、多額の自己資金を用意できる人は多くありません。日本政策金融公庫の創業融資制度は、自己資金が少なくても、事業計画の内容によっては融資を受けられる可能性があります。
自己資金の要件が厳しくないため、資金調達のハードルが低く、より多くの人が利用しやすい制度となっています。また、「スタートアップ起業・開業する業種の経験が豊富・公庫が推奨するセミナーを受講する」などの条件を満たせば、自己資金要件はさらに緩和されます。
6)審査期間が短い
事業をはじめるにあたって、迅速な資金調達は非常に重要です。日本政策金融公庫の創業融資制度は、審査期間が比較的短く、スムーズに資金調達を進めることができます。
審査期間は10日〜2週間、着金まで3週間〜1カ月半が目安となります。保証付融資などとくらべると、審査期間が短い傾向にありますが、必要書類がそろってからの入金になるので、早めの準備を心がけましょう。
7)融資制度が充実している
「女性、若者/シニア起業家支援資金」や「再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)」など、日本政策金融公庫の融資制度は幅広く、さまざまな人や業種に対応しています。
これらの制度は、それぞれの対象者に特化した内容となっており、より有利な条件で融資を受けられる可能性があります。融資の申請時にどの制度を使うか悩むかも知れませんが、担当者が各代表者・会社に応じて、最適な融資制度を提案してくれますので安心してください。
起業を志す皆様にとって、日本政策金融公庫の創業融資制度は、非常に魅力的な選択肢といえるでしょう。積極的に活用し、夢の実現に向けて力強く歩みを進めてください。
3.開業資金を借入れる際の注意点
開業資金の借入れは、起業を成功させるための重要なステップですが、注意すべき点もいくつかあります。スムーズに融資を受け、事業を軌道に乗せるために、以下の点に留意しましょう。
1)開業後3カ月以内に申請する
融資を申し込むタイミングは、見落としがちですが、非常に重要です。開業前か、開業後3カ月以内に申請することを意識しましょう。
開業前の段階では、自己資金の金額や事業計画の内容で審査されるので、もっとも審査に通りやすいタイミングといえます。
一方、開業後に時間が経過しすぎると、今度は実績に基づいた審査となり、ハードルが高くなります。金融機関は、過去の財務諸表や納税状況などを確認し、返済能力をきびしく審査します。
開業後3カ月以内であれば、事業計画の内容に加えて、開業後の状況も考慮してもらえる可能性があります。売上や顧客獲得の状況など、初期の事業活動が順調に進んでいることをアピールすることで、融資を受けやすくなるでしょう。
4.創業融資に必要な事業計画書の作成なら「ドリームゲート」
起業を成功させるためには、適切な資金調達方法を選択することが重要です。自身の事業計画や資金ニーズに合わせて、最適な融資制度を選びましょう。
当記事では、銀行以外にも、政府系金融機関や信用金庫・信用組合など、さまざまな開業資金の借入方法を紹介しました。それぞれのメリット・デメリットを理解し、賢く資金調達を進めていきましょう。
融資申請においてもっとも重要なのは、説得力のある事業計画書の作成です。しかし、はじめて事業計画書をつくるときには、何から手をつけてよいかわからず途方にくれる方が多いのではないでしょうか?
時間と手間をかけても、融資担当者が納得する計画書をつくるのは大変です。
そんなときには、事業計画書作成ツールがおすすめです。ドリームゲートの事業計画書作成ツールを使えば、ブラウザ操作だけで、12業種に対応した高品質な事業計画書を作成できます。無料なので、まずは使ってみましょう。
起業の準備は、決して楽ではありません。しかし、しっかりと計画を立て、適切な資金調達をおこなうことで、夢の実現に近づくことができます。当記事が、起業を志す皆様の道しるべとなれば幸いです。
- 累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる
- 12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定

元日本政策金融公庫の融資課長として5000名以上の起業家を支援した上野アドバイザー。現在は、資金調達の専門家として活躍されております。融資を検討されている方はぜひご相談ください。
著書「事業計画書は1枚にまとめなさい」「起業は1冊のノートから始めなさい」など。
プロフィールを見る>>