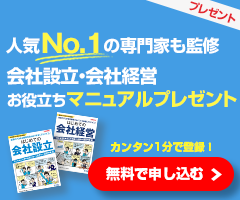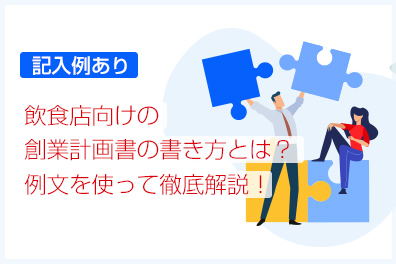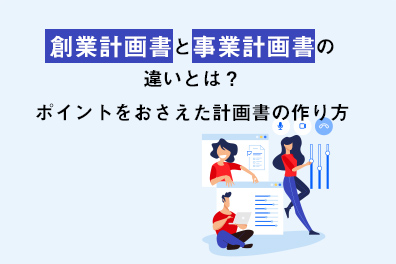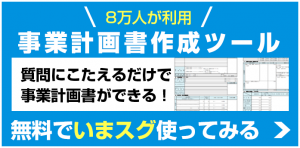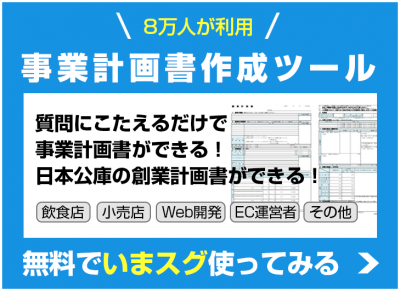開業時に利用できるおすすめの創業融資制度を起業のプロが徹底解説
開業という大きな一歩を踏み出す皆さまは、事業への期待と熱意に満ちあふれていることでしょう。しかし、その夢を現実のものとするためには、まず「資金の壁」を乗り越えなければなりません。
とくにはじめての起業では、自己資金だけでは不足することが多々あります。そこで、あなたの起業を強力に後押ししてくれる制度が創業融資です。創業融資は、これから事業をはじめる方を支援するための心強い資金調達手段です。
本記事では、数多くの起業家を支援してきたコンサルタントが、創業融資の主要な制度から、成功のための秘訣まで、徹底的に解説します。本記事を読み終えるころには、あなたの事業に最適な資金計画が描けるはずです。本記事を活用し、夢の実現に向けた第一歩を踏み出しましょう。
8万人が利用した事業計画書作成ツール
ブラウザ上の操作で事業計画を作成、創業計画書もエクセルでダウンロード可能
元日本政策金融公庫の融資課長として5000名以上の起業家を支援した上野アドバイザー。現在は、資金調達の専門家として活躍されております。融資を検討されている方はぜひご相談ください。
著書「事業計画書は1枚にまとめなさい」「起業は1冊のノートから始めなさい」など。
プロフィールを見る>>
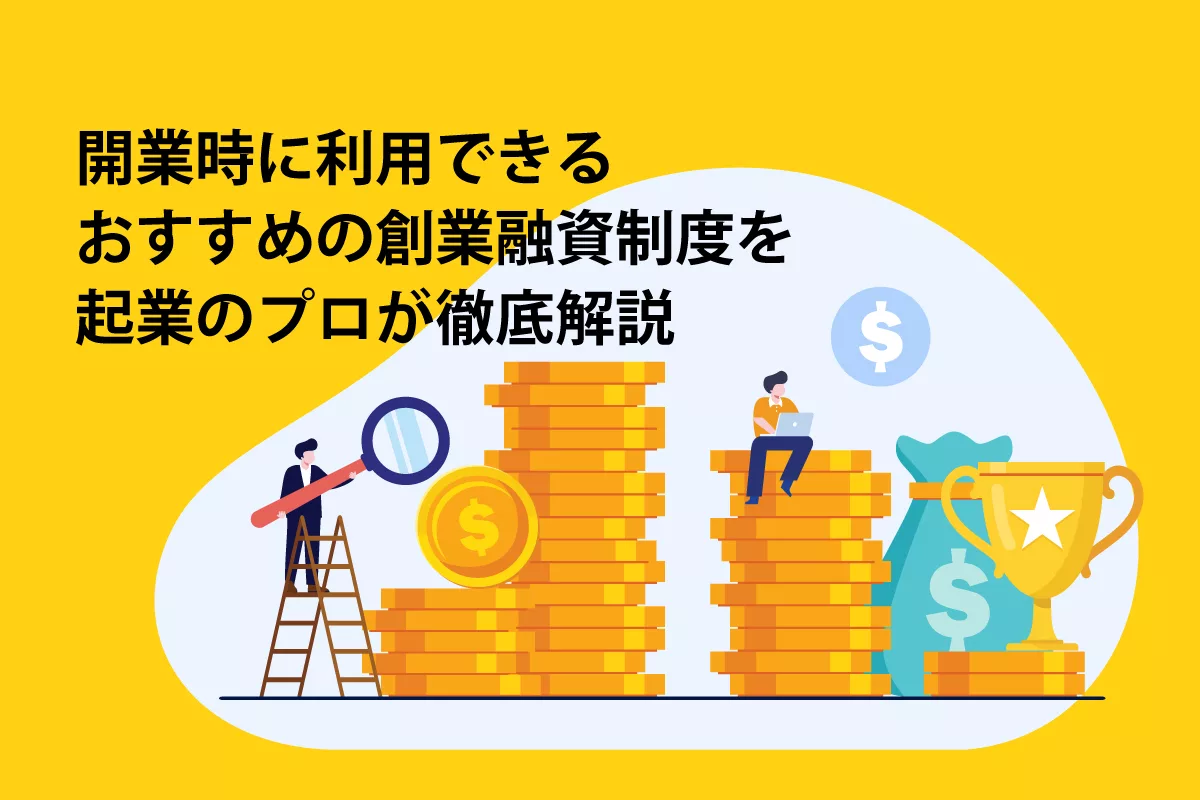
目次
1.そもそも創業融資とは
創業融資とは、これから事業をはじめる方や、事業を開始して間もない方を対象とした融資制度の総称です。一般的な事業資金融資と比較して、開業前後の実績がない時期でも利用しやすいように設計されている点が大きな特徴です。
創業期は売上や利益の実績がないため、民間金融機関から融資を受けるのは困難なケースが少なくありません。そこで、国や地方自治体が提供する制度を活用することで、比較的低金利で長期的な資金調達が可能になります。
創業融資は、単に事業資金を調達するだけでなく、事業計画の実現可能性や経営者の熱意を金融機関に示すよい機会ともいえるでしょう。
2.創業融資におすすめの制度
創業融資を検討する際、多くの選択肢が存在するため、どの制度を選べばよいか迷う方も多いでしょう。しかし、結論からいえば、まずは日本政策金融公庫の制度を検討することがもっとも一般的で有効な手段です。
もちろん、公庫以外にも地方自治体の制度融資など、活用できる制度はいくつかあります。本章では、創業融資において、とくに利用をおすすめしたい3つの制度について、その特徴と活用法をくわしく解説します。
1)日本公庫の新規開業・スタートアップ支援資金
創業融資を考える際、最初に検討すべきなのは日本政策金融公庫(以下、日本公庫)の融資制度です。日本公庫は、政府が100%出資する政府系金融機関であり、民間の金融機関では対応しきれない部分を補完する役割を担っています。創業融資の場合、とくに「新規開業・スタートアップ支援資金」が一般的に利用されます。
この制度は、事業実績のない創業者でも利用しやすいよう設計されており、比較的低金利で長期の返済期間が設定されることが多いです。また、融資限度額も大きいため、まとまった資金が必要な場合に適しています。
ただし、どの制度を適用するかは最終的に日本公庫の担当者が判断するため、申請者自身が制度名を強く意識する必要はありません。重要なのは、質の高い事業計画書を作成し、担当者に事業の将来性を納得させることです。
2)信用保証協会付き融資
日本公庫以外の民間金融機関から創業融資を受ける場合、基本的には信用保証協会付き融資が多くなります。信用保証協会は、中小企業や小規模事業者が金融機関から融資を受ける際に、その借入を保証する公的機関です。
万が一、事業が立ち行かなくなり返済ができなくなった場合、信用保証協会が金融機関に代位弁済(肩代わり)します。これにより、金融機関は貸し倒れのリスクをおさえることができ、実績の少ない創業者に対しても融資しやすくなります。
また、この制度を利用する場合、まずは信用保証協会に相談に行くという選択肢もあります。保証を受けることで、民間金融機関との交渉がスムーズに進む可能性が高まります。
3)地方自治体の制度融資
各地方自治体には、地域経済の活性化を目的とした独自の融資制度が設けられています。これらの地方自治体の制度融資は、創業資金を支援するために、低金利や保証料の補助といった融資条件の優遇が設定されていることが多いです。多くの場合、信用保証協会が保証を提供し、金融機関が融資を実行するスキームが採用されています。
地方自治体の制度融資は、特定の地域で開業する事業者を支援する目的があるため、居住地や事業所所在地がその自治体内にあることが条件となります。自治体によって制度内容や条件が異なるため、まずは開業を予定している地域のウェブサイトや商工会議所に相談し、どのような制度があるか確認してみるのがよいでしょう。
- 累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる
- 12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定
3.創業融資の成功のために知っておくべきこと
創業融資の成功確率を高めるためには、制度の概要を理解するだけでなく、金融機関の考え方や審査のポイントを把握しておくことが重要です。ここでは、コンサルタントとして多くの起業家を支援してきた経験から、とくに知っておくべき5つのポイントを解説します。
1)日本公庫は協調融資に積極的
前述したとおり、日本公庫は政府系金融機関であり、あくまで民間金融機関をサポートする立場です。そのため、日本公庫は「協調融資」に非常に積極的です。協調融資とは、複数の金融機関が共同で融資をおこなうことを指し、日本公庫から創業融資が決定すると、その実績はほかの金融機関にとって大きな信用となります。
日本公庫が事業計画を評価し、融資を実行したという事実は、その事業の将来性や経営者の信用性を証明するものとみなされ、信用保証協会の審査がとおりやすくなる傾向にあります。
この効果を最大限に活用するために、日本公庫からの借入金は、次に協調融資を検討している金融機関の口座に入金することをおすすめします。これにより、取引実績ができ、その後の関係構築をスムーズに進めることができます。
2)事業開始前に申請すべし
事業開始前であれば、事業計画書や創業者個人の信用情報が主な審査対象となり、将来性や熱意が評価されます。
一方、事業開始後になると、じっさいの事業実績(売上や利益など)も審査に加味されるだけでなく、事業計画書の内容と実績との整合性も問われます。そのため、事業開始から間もない時期が、創業融資を申請する最適なタイミングといえるでしょう。
3)創業者個人の信用が重要
創業融資の審査では、事業の収益性や将来性はもちろんですが、それ以上に創業者個人の信用が非常に重要視されます。なぜなら、事業の実績がない時点では、融資の返済能力を判断するうえで、創業者自身の返済履歴や信用情報が重要な指標となるからです。
具体的には、過去の所得や貯蓄額、住宅ローンや自動車ローン、クレジットカードの支払いに滞りがないか、納税をきちんとおこなっているかなどが厳しくチェックされます。自己資金の割合も重要なポイントです。
開業資金の一定割合を自己資金で賄うことで、事業への本気度や計画性をアピールできます。日ごろから健全な金銭管理を心掛けることが、創業融資成功への第一歩といえるでしょう。
4)士業からの紹介が強い
創業融資の申請を検討する際、税理士や経営コンサルタントに相談するケースも多いかと思います。彼らは独自のネットワークを構築していることが多く、金融機関の担当者と顔見知りであることも少なくありません。創業融資の審査は、最終的に金融機関の担当者との人間関係や信頼関係が鍵を握ることがあります。
税理士などの士業からの紹介であれば、単なる一顧客ではなく、専門家が事業計画を精査し、そのうえで紹介しているという信用が加わります。この信用は非常に強力であり、融資の成功確率を格段に引き上げてくれる可能性があります。
5)将来のプロパー融資につながるか
創業融資は、一度受ければそれで終わりというものではありません。事業が成長し、資金需要がさらに拡大した際に必要となるプロパー融資(金融機関からの直接融資)の道筋をつけることが重要です。信用保証協会付き融資は、あくまで保証協会が保証してくれるから融資が受けられる制度です。
将来的にプロパー融資を受けたいのであれば、信用保証協会の保証枠を使う金融機関の選定も戦略的におこなうべきです。プロパー融資に前向きな姿勢があり、事業規模が拡大しても対応してくれるような金融機関を選ぶようにしましょう。
一方で、プロパー融資に積極的でない小規模な信用金庫や信用組合には注意が必要です。長期的な視座を持って、金融機関との関係を構築することが成功への鍵となります。
- 累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる
- 12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定
4.創業融資以外の資金調達方法
創業資金の調達方法は、創業融資だけではありません。事業の特性や規模、そして経営者の考え方に応じて、さまざまな選択肢を検討することが可能です。
ここでは、創業融資以外で利用できる代表的な資金調達方法をいくつかご紹介します。これらの方法も視野に入れ、ご自身の事業に最適な資金調達計画を立ててください。
1)貯蓄
もっとも基本的で確実な資金調達方法が、自身の貯蓄です。日ごろから計画的に貯金しておくことはもちろん、ボーナスや臨時収入を開業資金に充てることも有効です。自己資金は、金融機関からの融資審査でも重要な評価項目となります。事業への本気度を示すためにも、できるだけ多くの自己資金を用意することが望ましいです。
2)補助金・助成金
国や地方自治体は、さまざまな目的で補助金・助成金制度を設けています。これらは返済の必要がないため、非常に魅力的な資金源となります。ただし、支給の要件が厳しく、審査に時間がかかること、そして後払いであることが一般的です。まず自己資金や融資で事業を開始し、後から補助金・助成金で補填するという考え方が現実的です。
3)エクイティファイナンス
成長が見込まれる事業であれば、ベンチャーキャピタル(VC)やエンジェル投資家からの出資を受ける方法もあります。これは、株式発行により資金を調達する方法であり、エクイティファイナンスと呼ばれます。
融資と異なり返済義務はありませんが、経営権の一部譲渡というデメリットが存在します。しかし、投資家から経営に関するアドバイスや支援を受けられるというメリットもあるため、両者を考慮したうえで検討することが必要です。
4)ビジネスコンテスト
多くの地方自治体や民間企業が、事業アイデアを競い合うビジネスコンテストを開催しています。入賞すれば、賞金や事業資金、そして事業のプロモーションにつながる機会を得ることができます。
5)クラウドファンディング
インターネットを通じて、不特定多数の人から資金を募るクラウドファンディングも、資金調達方法のひとつとして認知が進んでいます。とくに、ユニークな商品やサービス、社会貢献性の高い事業などで有効な手段です。支援者とのコミュニケーションを通じて、事業のファンを獲得できるというメリットもあります。
5.創業融資の成功アップはドリームゲートの事業計画書作成サポートツール
本記事では創業融資の主要な制度と、成功のための重要なポイントについて解説してきました。創業融資における事業計画書は、金融機関担当者に事業の可能性を伝えるためのもっとも重要な書類です。説得力のある事業計画書を作成することは、創業融資の成功を大きく左右します。
創業融資の成功確率を高めるためには、ドリームゲートの「事業計画書作成サポートツール」の利用をおすすめします。このツールは、専門的な知識がなくても、質問に答えるだけで論理的かつ説得力のある事業計画書を作成できる優れものです。
多くの起業家が利用し、融資獲得の実績を上げています。創業融資の成功確率を少しでも高めたいとお考えの方は、ぜひ活用を検討してみてはいかがでしょうか。

元日本政策金融公庫の融資課長として5000名以上の起業家を支援した上野アドバイザー。現在は、資金調達の専門家として活躍されております。融資を検討されている方はぜひご相談ください。
著書「事業計画書は1枚にまとめなさい」「起業は1冊のノートから始めなさい」など。
プロフィールを見る>>