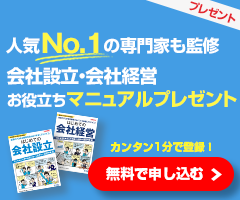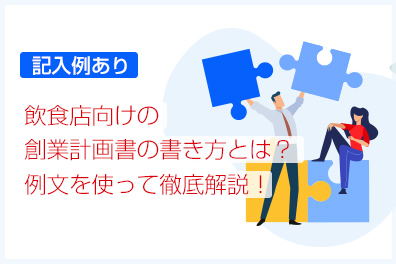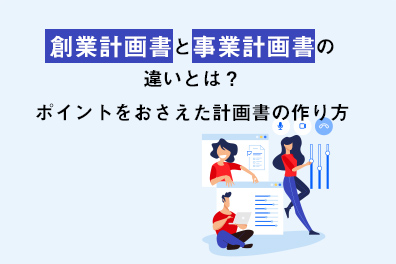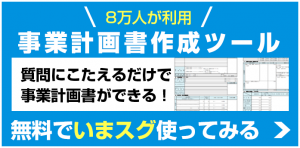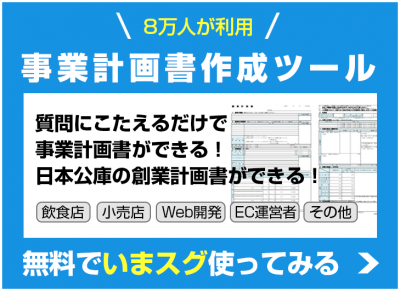創業融資の上限と融資額を引き上げる方法を起業のプロが解説!
新たな事業をはじめるにあたって、資金調達は起業家の皆様が直面するもっとも重要な課題のひとつといえるでしょう。とくに創業期の資金繰りは、事業の成否を大きく左右する要因となります。
自己資金だけではまかないきれない設備投資や運転資金をどのように確保するかは、多くの起業家にとって共通の悩みです。しかし、創業融資制度を適切に理解し活用することで、そのハードルは大きく下がります。
そこで本記事では、創業融資の限度額と、より多くの資金を調達するための具体的な方法について、実践的な視点から詳細に解説します。皆様の事業が力強く成長するための確かな一歩を踏み出す一助となれば幸いです。
8万人が利用した事業計画書作成ツール
ブラウザ上の操作で事業計画を作成、創業計画書もエクセルでダウンロード可能
元日本政策金融公庫の融資課長として5000名以上の起業家を支援した上野アドバイザー。現在は、資金調達の専門家として活躍されております。融資を検討されている方はぜひご相談ください。
著書「事業計画書は1枚にまとめなさい」「起業は1冊のノートから始めなさい」など。
プロフィールを見る>>

目次
1.創業融資の上限は金融機関や融資制度によってちがう
創業融資を検討する際、選択肢としてまず挙げられるのが、日本政策金融公庫や信用保証協会の保証付き融資です。これに対し、いきなり一般の銀行からプロパー融資を受けることは、創業間もない企業にとっては極めて困難であるといわざるをえません。
金融機関は実績や信用を重視するため、事業の実態がまだ確立されていない創業期においては、公的機関の制度を活用することが現実的な選択肢となるのです。それぞれの制度には、異なる特徴と融資上限額が設定されており、自社の状況に最適な選択をすることが重要となります。
1)日本政策金融公庫
創業融資を検討する場合、日本政策金融公庫は多くの起業家にとって最初の候補となるでしょう。その最大の魅力は、原則として無担保・無保証で融資を受けられる点にあります。これは、個人保証によるリスクを避けたい起業家にとって非常に大きなメリットとなります。
また、公庫からの融資が決定すれば、信用金庫などで法人口座を開設しやすくなるという副次的なメリットも期待できます。公庫の審査をクリアできたという事実は、ほかの金融機関からの信頼を得るうえでも有効に作用するからです。
参考:日本政策金融公庫での創業融資の申し込みの全てを融資の専門家が徹底解説
①新規開業・スタートアップ支援資金は7,200万円
日本政策金融公庫の代表的な創業融資制度のひとつに「新規開業・スタートアップ支援資金」があります。この制度における融資限度額は、事業に必要な設備資金と運転資金を合わせて最大で7,200万円となり、そのうち運転資金の上限は4,800万円となります。
ただし、この額はあくまで制度上の上限額であり、じっさいにここまで借入れできるケースは稀であると認識しておく必要があります。事業計画の内容や自己資金の状況など、さまざまな要素が総合的に判断されます。
②融資制度は担当者が決める
公庫に融資を申込む際、どの融資制度が適用されるかは、融資担当者の判断に委ねられる部分が大きいのが実情です。起業家が特定の制度を希望しても、事業の内容や申込者の状況に応じて、担当者が最適な制度を選択し提案してくることが一般的です。
そのため、事前に各制度の特徴を把握しつつも、面談時には担当者とのコミュニケーションを通じて、自身の事業にもっとも合致する融資制度を引き出す努力が求められます。
③支店長の決裁権限枠がある
日本政策金融公庫の場合、創業融資に限らず、各支店長の決裁権限枠がある点に注意が必要です。その金額は公開されていませんが、一定金額を超える融資案件については、支店長以上の決裁が必要となることを意味します。
実態としては、創業融資で1,000万円以上の借入れを実現することは、ハードルが高いと考えた方がよいでしょう。
2)信用保証協会
信用保証協会は、中小企業が金融機関から融資を受ける際に、その債務を保証する公的機関です。地方自治体の制度融資も信用保証協会を利用しているため、こちらも創業期の資金調達における重要な選択肢となります。また、公庫と比較すると、審査が緩やかであると感じる起業家も少なくありません。
参考:創業融資における信用保証協会の役割とは?|資金調達のプロが公庫と徹底比較
①創業融資では3,500万円
信用保証協会が保証する創業融資の限度額は、通常3,500万円とされています。これも公庫と同様、あくまで上限額であり、じっさいにこの金額まで融資が実行されるケースは多くありません。
ただし、信用保証協会の保証があれば、民間の金融機関からの融資が受けやすくなるという大きなメリットがあります。金融機関は保証があることでリスクを低減できるため、積極的に融資を検討するようになるのです。
法人の場合、「スタートアップ創出促進保証制度」に該当すれば、代表者の個人保証が不要の融資を利用することができます。
②保証協会枠は全体で2億8,000万円
信用保証協会による保証枠は、創業融資に限らず、企業の総借入額に対して設定される全体枠として2億8,000万円(普通保証2億円、無担保保証8,000万円)まで利用できる可能性があります。これは、創業後も事業の成長に合わせて追加の融資を受ける際に、この保証枠を活用できることを意味します。
しかし、どの金融機関で保証協会の枠を使うかは戦略的に考える必要があります。たとえば、信用金庫だけでなく、将来的に大きな金額のプロパー融資に繋がる可能性のある地方銀行とも取引を開始し、バランス良く保証枠を活用していくことが賢明な経営判断といえるでしょう。複数の金融機関と良好な関係を築くことで、資金調達の選択肢を広げることができます。
2.創業融資で借りられる金額の目安
創業融資において、「必ずしも上限まで借りられるわけではない」という前提を理解しておくことは非常に重要です。制度上の限度額が設定されていても、じっさいに借入れできる金額は「事業の内容、経営者の実績、自己資金の有無、そして事業計画の具体性」によって大きく左右されます。
夢だけが先行して、現実離れした融資額を希望しても、金融機関の審査を通過することは困難です。現実的な視点を持って、必要な資金と実現可能な融資額を見極めることが肝要となります。
1)平均は800万円程度
日本政策金融公庫の統計データなどを見ると、創業融資の平均額は800万円弱に収まることが多いとされています。これは、さまざまな事業規模や業種の起業家が融資を受けている結果としての平均値であり、ひとつの目安として捉えることができます。
どのような素晴らしい事業計画を提示したとしても、500万円から1,000万円程度の範囲が、多くの創業融資における現実的な落とし所となるでしょう。この範囲内であれば、金融機関も比較的リスクを許容しやすい傾向にあります。
2)必要な金額から自己資金を差し引いた金額
金融機関が融資をおこなう際にもっとも重視するのは、その資金が事業にとって本当に必要なのかどうか、そしてその必要性が具体的にどのように算出されているかという点です。したがって、創業融資で借りられる金額は、事業運営に必要となる総資金から、すでに準備している自己資金を差し引いた金額が基本的な考え方となります。
当たり前のことではありますが、金融機関は事業に必要な分しか貸し付けません。過剰な借入れは、将来の返済負担を増大させ、経営を圧迫するリスクとなるため、堅実な資金計画が求められます。
3)自己資金の3倍程度
創業融資に限らず、融資の一般論として、自己資金の3~4倍程度までが借入れの限度という目安があります。つまり、総事業費に対して自己資金が3割程度準備されていると、金融機関からの評価が高まり、融資を受けやすくなる傾向にあるということです。
これは、経営者の本気度や、事業に対するリスク許容度を示す指標として捉えられます。自己資金が潤沢であればあるほど、金融機関は安心して融資をおこなうことができるため、可能な限り自己資金を準備しておくことが、希望する融資額を獲得するための重要なポイントとなります。
- 累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる
- 12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定
3.創業融資で融資額を引き上げるためのポイント
創業融資において、融資金額を最大限に引き出すためには、いくつかの重要なポイントをおさえる必要があります。ただし、ここで常に念頭におくべきは、「過度な借入れは経営リスクになる」という前提です。
必要以上の資金を借入れることは、将来的に返済負担が重くのしかかり、経営を圧迫する要因となりかねません。適切な資金計画のもと、着実に事業を成長させるための資金調達を目指しましょう。
1)経営者の実績を強調する
創業期の事業に対する評価が難しいため、金融機関は経営者自身の経歴や実績を重視します。過去に携わった事業での成功体験、業界での専門知識、マネジメント経験など、自身の強みとなる実績を具体的にアピールすることが重要です。
とくに、新規事業と関連性の高い分野での実績は、事業の実現可能性を高めるものとして高く評価される傾向にあります。自身の持つスキルや経験が、いかに新事業の成功に寄与するかを説得力のある言葉で伝えることが求められます。
2)現実的な事業計画書を作成する
融資審査において、事業計画書はもっとも重要な書類のひとつです。夢物語のような非現実的な計画ではなく、市場分析に基づいた具体的な「顧客層、競争優位性、収益モデル、資金使途、返済計画」などを明確に記述することが不可欠です。
売上予測や利益計画も、根拠に基づいた現実的な数値を提示し、その実現可能性を論理的に説明できる必要があります。金融機関の担当者が納得できる、説得力のある事業計画書を作成することが、融資額を引き上げるための鍵となります。
3)資金使途を明確にする
借入れた資金を何に使うのか、その使途を具体的に、かつ明確に示すことは極めて重要です。設備投資であれば具体的な機器の名称や導入費用、運転資金であれば仕入れ費用や人件費の内訳など、詳細に説明できる準備が必要です。
資金使途が明確でなければ、金融機関は資金の使われ方を懸念し、融資に慎重になります。使途が明確で、かつそれが事業の成長に直結することが論理的に説明できれば、融資担当者も前向きに検討する材料となります。
4)自己資金を準備する
前述のとおり、自己資金の存在は、経営者の本気度とリスク許容度を示す重要な指標となります。自己資金が潤沢であればあるほど、金融機関は安心して融資を実行することができます。
総事業費の3割程度の自己資金を準備することが理想的とされています。そのため、可能な範囲で多くの自己資金を確保することが、希望する融資額に近づくための強力な要素となります。また、自己資金の形成過程も重要視されるため、計画的に貯蓄した資金であることを証明できるよう準備しておきましょう。
5)創業後3カ月以内に申請する
創業融資を検討しているのであれば、創業前か、創業後できるだけ早い段階で申請することをおすすめします。具体的には、創業後であれば3カ月以内を目安に申請を検討することが望ましいでしょう。
創業後ある程度の時間が経過すると、金融機関は過去の実績を求めはじめるため、創業する前かまだ実績が少ない創業直後のほうが、将来性や事業計画の具体性に基づいて融資を判断してもらいやすくなります。事業を開始する前に、融資申請の準備を進めておくことが賢明な判断といえるでしょう。
4.創業融資はドリームゲートの事業計画書作成サポートツールがおすすめ
創業融資の成功には、説得力のある事業計画書の作成が不可欠ですが、ゼロから作成するのは非常に労力がかかります。そこで、多くの起業家にとって心強い味方となるのが、ドリームゲートが提供する事業計画書作成サポートツールです。
このツールは、事業計画書のひな形や例文、具体的な作成手順を提供しており、効率的に質の高い事業計画書を作成するのに役立ちます。専門的な知識がなくても、ガイドにしたがって入力することで、金融機関に提出できるレベルの計画書が作成可能となります。
創業融資の成功確率を高めるためにも、支援ツールの活用を積極的に検討してみてはいかがでしょうか。
- 累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成
- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる
- 12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定

元日本政策金融公庫の融資課長として5000名以上の起業家を支援した上野アドバイザー。現在は、資金調達の専門家として活躍されております。融資を検討されている方はぜひご相談ください。
著書「事業計画書は1枚にまとめなさい」「起業は1冊のノートから始めなさい」など。
プロフィールを見る>>